はじめに
広汎性発達障害は、社会性やコミュニケーション能力、想像力の障害など、さまざまな特徴を持つ発達障害の一種です。様々な症状や困難に直面する当事者の方々を理解し、適切な支援を行うことが重要とされています。本稿では、広汎性発達障害について、症状、原因、診断、就労支援など、多角的な観点から詳しく解説していきます。
広汎性発達障害の症状とは

広汎性発達障害には、さまざまな症状がみられます。代表的な症状として、以下のようなものが挙げられます。
社会性・対人関係の障害
他者との適切な関係を築くことが難しく、孤立しがちです。人の気持ちを読み取ることや、相手の立場に立って考えることが苦手です。また、人混みや騒がしい環境を苦手とする傾向があります。
社会性の障害は、広汎性発達障害の中核的な特徴の一つです。周囲の人々との積極的な関わりを避け、一人で過ごすことを好むなど、社会的なつながりを持つことが困難な様子がみられます。
コミュニケーションの障害
言葉の使い方や意味の理解が難しく、適切なコミュニケーションがとれないことがあります。会話の主題をそれず、独り言が多かったり、言葉の発音が不明瞭だったりするなどの特徴もみられます。
コミュニケーション能力の障害は、広汎性発達障害の大きな特徴です。言葉の理解が一語文字通りであったり、比喩的な表現が分からなかったりするなど、言語の使用に困難を抱えがちです。また、視線を合わせることが苦手だったり、身振りや表情の読み取りが難しかったりするため、非言語コミュニケーションにも支障がでることがあります。
こだわりやパターン化した行動
特定の物事や行動にこだわり、それ以外を受け入れられない強いこだわりを持つことがあります。また、決まった習慣や行動パターンを守ろうとし、予定の変更に対して強い不安を感じることもあります。
広汎性発達障害のある人は、特定の興味関心に集中し、それ以外のことに関心が向かないことが多くみられます。また、日々の生活リズムや行動パターンを維持したい傾向があり、少しの変化にも強い不安を覚えてしまいます。
広汎性発達障害の原因
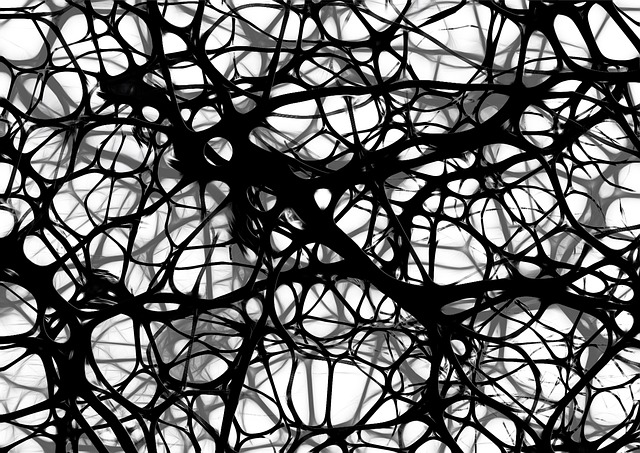
広汎性発達障害の原因は、まだ明確にはわかっていませんが、様々な要因が関係していると考えられています。
遺伝的要因
遺伝的要因が大きく関係していると考えられています。双子研究から、一卵性双生児の場合には両方に発症するリスクが高く、それ以外の場合のリスクはそれより低いことがわかっています。
また、近年の研究では、自閉症スペクトラム症の原因遺伝子候補として100を超える遺伝子が特定されており、遺伝的要因が大きな役割を果たしていることが明らかになってきました。
環境的要因
妊娠中の母体の状態や、出生時の環境なども関係していると考えられています。具体的には、母体の高齢出産、感染症、薬物の影響、低出生体重など、様々な要因が挙げられています。
しかし、これらの要因があっても必ずしも広汎性発達障害が発症するわけではありません。遺伝的要因と環境的要因が複雑に関係し合って発症すると考えられています。
脳の発達の違い
広汎性発達障害のある人の脳の構造や機能に違いがあることがわかってきました。特に、社会的認知や情動に関わる領域の発達に何らかの問題があると考えられています。
MRI画像を用いた研究から、広汎性発達障害のある人の脳の一部の領域の体積が異なることや、神経回路の異常があることなどが明らかになってきました。このような脳の発達の違いが、症状の原因になっていると考えられています。
広汎性発達障害の診断

広汎性発達障害の診断は、行動観察や発達検査、質問紙調査などを総合的に行うことで決定されます。現時点では特異的な医学的検査はありません。
症状の早期発見
広汎性発達障害の症状は、通常1歳半〜3歳頃から現れ始めます。この時期に、以下のような症状がみられた場合は、専門家に相談することが推奨されています。
- 指さしに反応しない
- 名前を呼んでも振り向かない
- 言葉の発達の遅れ
- 特定の物事にひたすら没頭する
- 常同的な行動を繰り返す
早期発見と早期療育が、その後の発達に良い影響を与えるとされています。周囲の方々が症状に気づき、専門家に相談することが重要です。
発達検査
幼児期の発達検査では、認知発達、言語発達、適応行動発達などを総合的に評価します。代表的な検査として、ウェクスラー幼児知能検査(WPPSI)やベイリー乳幼児発達スケールなどがあります。
学齢期以降は、ウェクスラー知能検査(WISC)が用いられることが多く、言語性知能と動作性知能を評価します。また、自閉症診断観察尺度(ADOS)やAQ(自閉症スペクトラム指数)検査なども活用されています。
診断のプロセス
以上の検査結果と合わせて、専門家が行動観察や両親への聞き取りなどを行い、総合的に診断が下されます。診断には、児童精神科医や発達障害の専門家が関わり、時間をかけてていねいにプロセスが進められます。
広汎性発達障害の支援と対応

広汎性発達障害のある方への支援は、年齢やライフステージに合わせて変化します。個別的な支援が必要不可欠であり、本人と家族、専門家がともに協力して取り組むことが大切です。
早期療育
早期から適切な療育を行うことで、症状の改善や二次的な問題の予防が期待できます。療育の方法として、以下のようなものがあります。
- 応用行動分析(ABA)による行動療法
- コミュニケーション能力を高める療育
- 感覚統合療法
- 遊びを通した社会性の訓練
一人一人の発達段階や個性に合わせた療育プログラムを作成し、きめ細かい支援を行うことが重要です。保護者への心理教育も欠かせません。
学齢期の支援
学齢期には、学校生活に適応できるよう、以下のような支援が求められます。
- 個別の指導計画の作成
- ソーシャルスキルトレーニング
- 気分転換の場所の設置
- 教職員への発達障害の理解促進
文字や絵を使った視覚支援や、予定の変更に備えての事前説明など、本人の特性に合わせた配慮が大切です。教科学習面での支援も欠かせません。
思春期・成人期の支援
思春期以降は、次のようなことが課題となります。
- 進路選択の支援
- 就労支援
- 自立生活のための訓練
- 余暇活動支援
- セカンドキャリアの支援
職場や社会生活への適応を図るため、具体的な支援が求められます。発達障害者支援センターや就労移行支援事業所の活用が効果的です。また、同じ境遇の当事者同士の交流の場も重要です。
まとめ
広汎性発達障害は、多様な特徴を持つ障害であり、一人一人に合わせた柔軟な対応が不可欠です。本人の特性を受容し、長所を伸ばしていくことが重要です。一方で、社会生活への適応をサポートすることも大切な課題となります。医療、教育、福祉などの専門家と協力し、本人や家族を含めた包括的な支援体制を整えることが望まれます。広汎性発達障害のある人が、「個性」を生かして社会で活躍できるよう、理解を深め、支援の輪を広げていきましょう。
よくある質問
広汎性発達障害の代表的な症状とは何ですか?
広汎性発達障害の主な症状には、社会性やコミュニケーションの障害、こだわりや常同行動などがあります。他者との適切な関係性を築くことが難しく、言葉の使い方や意味の理解にも困難を抱えがちです。また、特定の興味関心に集中し、予定の変更に強い不安を感じる傾向があります。
広汎性発達障害の原因はわかっていますか?
広汎性発達障害の原因は明確ではありませんが、遺伝的要因と環境的要因が複雑に関係していると考えられています。遺伝的な要因が大きく関係しており、脳の構造や機能に何らかの違いがあることも明らかになってきました。
広汎性発達障害の診断はどのように行われますか?
広汎性発達障害の診断は、行動観察や発達検査、質問紙調査などを総合的に行って決定されます。発達検査では、認知、言語、適応行動などを評価し、自閉症診断観察尺度(ADOS)やAQ検査なども活用されます。専門家による丁寧な診断プロセスを経て、診断が下されます。
広汎性発達障害のある人への支援にはどのようなものがありますか?
広汎性発達障害のある人への支援は、年齢やライフステージに応じて変化します。早期から適切な療育を行うことで、症状の改善や二次的な問題の予防が期待できます。学齢期には学校生活への適応支援が、思春期以降は就労や自立生活への支援が必要となります。専門家と本人・家族が協力し、きめ細かい支援体制を整えることが重要です。


