はじめに
発達障害のある子どもや大人は、気持ちの切り替えが難しいという課題に直面することが多くあります。この課題は、発達障害の特性から生じる「見通しを立てる力の弱さ」「こだわりの強さ」「感情のコントロールの難しさ」などが複合的に影響しているためです。気持ちの切り替えができないことは、日常生活や対人関係、学校生活などさまざまな場面で支障をきたす可能性があります。本記事では、発達障害の方々が気持ちの切り替えに困難を感じる理由や対処法、周りの人々ができる配慮について、詳しく解説していきます。
気持ちの切り替えが難しい理由
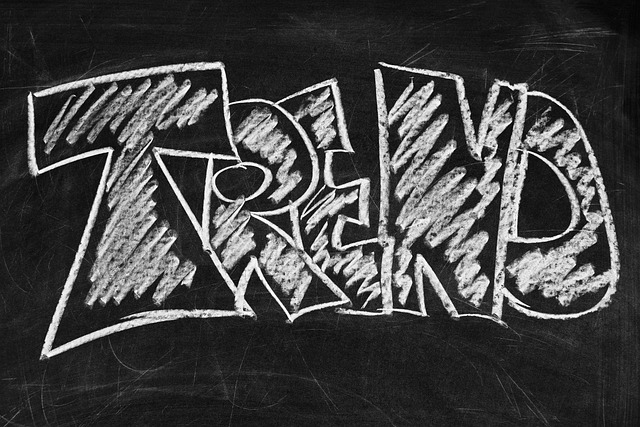
発達障害のある人が気持ちの切り替えに苦労する背景には、さまざまな要因が関係しています。ここでは、主な理由について掘り下げて説明します。
見通しを立てる力の弱さ
発達障害のある人は、次に何をすべきかを予測することが苦手です。そのため、現在の活動から次の活動へ移行するとき、スムーズに切り替えられずに混乱してしまいがちです。具体的には、遊びから宿題に移る際や、学校から家に帰る際など、日常生活の中で頻繁に見通しを立てる必要がある場面で、切り替えに困難を感じることがあります。
この課題に対処するためには、予定を事前に伝えたり、視覚的な手がかりを用意したりすることが有効です。スケジュール表やチェックリストを活用して、次に何をするべきかを明確にすることで、切り替えに対する不安を軽減できます。
こだわりの強さ
発達障害のある人は、特定のものや行動にこだわりを持つ傾向があります。好きな活動に夢中になってしまい、次の行動に移れないケースがよくあります。例えば、ゲームやテレビ視聴、お気に入りの玩具で遊ぶことから離れられず、食事の時間や就寝時間が遅くなってしまうなどの問題が生じます。
こだわりへの対処としては、早めに予告をして気持ちの切り替えを促したり、こだわりの行動を一定時間許容した上で、その後は別の活動に移るよう促したりするのが効果的です。また、こだわりの行動自体を否定するのではなく、一定の時間内で許容することが大切です。
感情のコントロールの難しさ
発達障害のある人は、感情のコントロールが苦手な傾向にあります。気分が乗らない活動に移る際に、イライラやフラストレーションを感じて感情的になりがちです。そのため、気持ちを切り替えられずに、現在の活動から離れられなくなってしまうのです。
この課題への対処には、自分なりの落ち着き方を見つけることが重要です。深呼吸をしたり、一人の時間を作ったり、好きな音楽を聴いたりするなど、自分に合った方法を見つけることで、感情をコントロールしやすくなります。また、周りの人が穏やかに言葉かけをすることも、気持ちの切り替えを促す一助となります。
気持ちの切り替えへの対処法

発達障害のある人が気持ちの切り替えに困難を感じる場合、本人や周りの人々がさまざまな対処法を取ることで、その課題を乗り越えることができます。ここでは、効果的な対処法について解説します。
周りの人々による配慮と支援
発達障害のある人が気持ちの切り替えに苦労している場合、周りの人々が適切な配慮や支援をすることが重要です。具体的には、次のようなことに気を付けましょう。
- 事前に予定を伝え、見通しを持たせる
- 視覚的な手がかり(スケジュール表やチェックリスト)を活用する
- 穏やかな言葉かけで、気持ちの切り替えを促す
- 一定の時間、こだわりの行動を許容する
- 感情を受け止め、落ち着くまで待つ
このように、発達障害のある人の特性を理解し、柔軟に対応することが大切です。焦らずに寄り添い、成功体験を積ませることで、徐々に気持ちの切り替えが上手くできるようになっていきます。
本人による対処法
発達障害のある人自身も、気持ちの切り替えに向けた対処法を身につけることが重要です。以下のような方法が効果的とされています。
- 自分なりの合言葉を決めて、気持ちの切り替えを促す
- 運動や散歩、ストレッチなどで体を動かす
- 好きな音楽を聴いたり、映画を観たりして気分転換を図る
- ジャーナリングを行い、感情を整理する
- 周りの人に助けを求める
このように、自分に合った方法を見つけながら、気持ちの切り替えに向けた工夫を続けることが大切です。周りの人々の支援を受けながら、試行錯誤を重ねていくことで、徐々にスキルが身につきます。
学校における配慮と支援
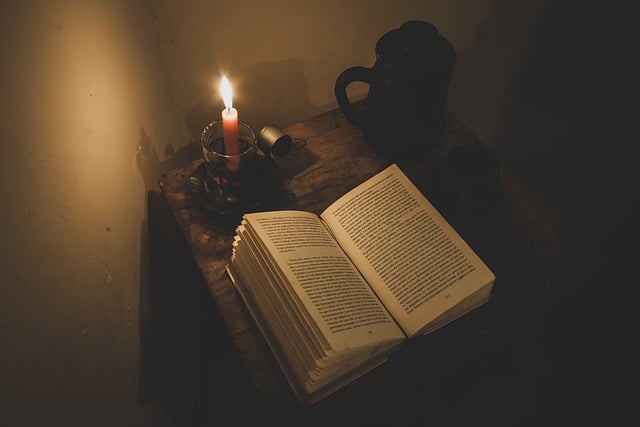
発達障害のある子どもが就学した場合、学校での配慮と支援が必要不可欠です。気持ちの切り替えが難しいため、集団生活に適応するのが困難になりがちだからです。ここでは、学校でどのような対応ができるかについて説明します。
個別の指導計画と合理的配慮
発達障害のある子どもに対しては、個別の指導計画を作成することが重要です。子どもの特性を踏まえた上で、具体的な指導方法や配慮事項を決めておくことで、スムーズな学校生活を送れるようサポートできます。
例えば、授業の切り替え時間にゆとりを持たせたり、活動の予告を事前にしたり、気持ちの切り替えに時間がかかることを理解して待つなどの配慮が考えられます。また、落ち着ける場所を設けたり、教師による穏やかな言葉かけを行ったりするのも効果的です。
教員への研修と理解促進
発達障害のある子どもに適切な指導ができるよう、教員への研修が不可欠です。発達障害の特性や、気持ちの切り替えの課題について理解を深めることで、より良い支援ができるようになります。
また、子どもの特性を理解してもらうことも大切です。「わがまま」や「甘え」と誤解されがちですが、それは発達障害の特性からくる課題であることを伝える必要があります。子どもの行動の背景にある思いに気づき、寄り添う姿勢が求められます。
保護者との連携
学校と保護者が連携して、一貫した支援を行うことが重要です。家庭での様子を把握した上で、学校でも同様の対応ができるよう情報を共有しましょう。また、保護者への理解啓発も欠かせません。
保護者会などの機会を活用して、発達障害の特性や気持ちの切り替えの課題について説明を行うことで、保護者の理解が深まります。そうすれば、子どもへの適切な支援と配慮が可能になり、集団生活への適応もスムーズになるはずです。
発達障害のある大人への配慮と支援

発達障害は、子どもだけでなく大人にもあります。気持ちの切り替えの課題は、就労や人間関係、生活面でも影響を及ぼします。ここでは、発達障害のある大人への配慮と支援について説明します。
職場での合理的配慮
就労している発達障害のある人に対しては、職場で合理的配慮を行うことが重要です。例えば、次のような対応が考えられます。
- 業務の切り替え時間にゆとりを持たせる
- 視覚的な手がかり(スケジュール表など)を活用する
- 言葉かけの際は、穏やかで分かりやすい表現を使う
- 職場の理解を促進するための研修を実施する
このように本人の特性に合わせて柔軟に対応することで、気持ちの切り替えをスムーズに行え、職場でのストレスを軽減できます。
地域での理解と支援体制
発達障害のある大人が地域で安心して生活できるよう、理解と支援体制の整備が求められます。自治体や福祉関係者、医療機関などが連携し、包括的な支援を行うことが重要です。
例えば、定期的な相談窓口の設置や、ピアサポーターによる交流の機会を設けるなどして、気持ちの切り替えなどの課題に向き合える場を提供することが考えられます。また、発達障害への正しい理解を促す啓発活動も欠かせません。
家族による寄り添い
発達障害のある家族には、本人の特性を理解し、寄り添うことが求められます。気持ちの切り替えに課題があることを受け入れ、焦らずに待つ姿勢が大切です。また、本人が気分転換できる環境を整えることも有効です。
例えば、落ち着ける場所を家の中に設けたり、趣味の時間を確保したりすることで、気持ちの切り替えがスムーズになる可能性があります。さらに、家族間でコミュニケーションを密に取り、発達障害の特性を踏まえた上で、本人への接し方を工夫していくことが重要です。
まとめ
本記事では、発達障害のある人が気持ちの切り替えに苦労する理由と、それに対する対処法や配慮事項について解説してきました。見通しを立てる力の弱さ、こだわりの強さ、感情のコントロールの難しさなどが、気持ちの切り替えに影響を与えています。
その課題を乗り越えるには、本人の特性を理解し、寄り添うことが何より重要です。周りの人々が適切な配慮と支援を行い、本人も自分に合った対処法を見つけていくことで、徐々に気持ちの切り替えが上手くできるようになっていきます。
発達障害は、一人ひとりの個性であり、多様性を認め合うことが大切です。互いを尊重し合いながら、本人らしく生きられる社会を目指していきましょう。
よくある質問
なぜ発達障害のある人は気持ちの切り替えが難しいのですか?
発達障害のある人は、次に何をすべきかを予測するのが苦手だったり、こだわりの強さから現在の活動から離れられなかったり、感情のコントロールが難しいなど、さまざまな要因が複合的に関係しているため、気持ちの切り替えが難しくなることがあります。
発達障害のある人の気持ちの切り替えをどのように支援すればよいですか?
周りの人が事前に予定を伝えたり、視覚的な手がかりを活用したりして見通しを持たせたり、穏やかな言葉かけで気持ちの切り替えを促したりするなど、本人の特性に合わせて柔軟に対応することが大切です。また、本人自身も自分に合った対処法を見つけながら、試行錯誤を重ねていくことが重要です。
学校ではどのように発達障害のある子どもの気持ちの切り替えを支援すればよいですか?
個別の指導計画を作成し、授業の切り替え時間にゆとりを設けたり、活動の予告を事前にしたりするなど、子どもの特性に合わせた具体的な配慮を行うことが大切です。また、教員への研修を通して発達障害の理解を深めてもらい、保護者との連携も図ることで、一貫した支援につなげていくことが重要です。
発達障害のある大人へはどのような支援が必要ですか?
就労している発達障害のある人に対しては、業務の切り替え時間にゆとりを設けたり、視覚的な手がかりを活用したりするなど、職場での合理的配慮が必要です。地域では、発達障害への理解を促す啓発活動や、相談窓口の設置などの支援体制を整えることが重要です。また、家族による本人の特性理解と寄り添いも欠かせません。


