はじめに
発達障害のある子どもたちが学校生活を送る上で、「通級指導」は重要な役割を果たしています。通級指導とは、発達障害のある児童生徒が通常の学級に在籍しながら、別室で専門的な指導を受けることです。本日は、通級指導の意義や実際の運用について詳しく解説していきます。
通級指導の概要

通級指導は、言語障害、自閉症、ADHD、学習障害など、様々な発達障害のある児童生徒を対象としています。ここでは、通級指導の目的や対象者、指導内容について解説します。
通級指導の目的
通級指導の主な目的は、発達障害のある児童生徒の学習上や生活上の困難を改善・克服することです。また、児童生徒の自己肯定感や学習意欲の向上も期待されています。通常の学級と別室での指導を併せて行うことで、児童生徒一人一人のニーズに合わせた適切な支援が実現できます。
さらに、通級指導を受けることで、児童生徒は通常の学級での学習や生活に円滑に参加できるようになります。つまり、通級指導は発達障害のある児童生徒が充実した学校生活を送るための重要な橋渡しの役割を果たしているのです。
通級指導の対象者
通級による指導の対象となる主な発達障害は以下の通りです。
- 言語障害
- 自閉症
- 情緒障害
- 学習障害
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
発達障害の程度によって、通級指導の利用の可否が判断されます。比較的軽度の発達障害のある児童生徒が対象となる傾向にあります。
通級指導の内容
通級指導の具体的な内容は、児童生徒一人一人の障害の状況や特性に応じて決められます。指導内容は個別の教育支援計画や指導計画に基づいてオーダーメイドされます。
例えば、以下のような指導が行われています。
- 読み書きや計算の指導
- コミュニケーション能力の向上支援
- 集団生活への適応支援
- 注意力や行動面での指導
- 感情のコントロール方法の指導
このように、通級指導では児童生徒一人一人の実態に合わせた細やかな支援が特徴的です。
通級指導の運用形態
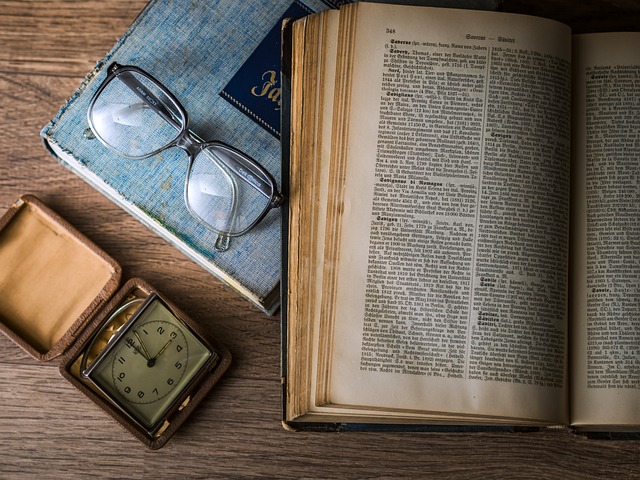
通級指導は、様々な形態で実施されています。ここでは、指導の実施形態や時間数、場所などについて解説します。
実施形態
通級指導には、以下の3つの実施形態があります。
| 形態 | 説明 |
|---|---|
| 自校通級 | 児童生徒が在籍する学校内で指導を受ける |
| 他校通級 | 児童生徒が在籍する学校以外の学校で指導を受ける |
| 巡回通級 | 指導員が複数の学校を巡回して指導を行う |
児童生徒の状況や学校の体制に合わせて、最適な形態が選択されます。
指導時間数
通級指導の時間数は、法令で以下のように定められています。
- 小中学校: 年間35単位時間~280単位時間
- 高等学校: 年間7単位時間以内で単位認定可能
学習障害や注意欠陥多動性障害の場合は、年間10単位時間~280単位時間の範囲で指導が行われます。指導時間数は児童生徒のニーズに応じて柔軟に設定されます。
指導場所
通級指導は、主に以下の2か所で行われています。
- 通級指導教室
- 通常の教室
通級指導教室は、児童生徒が落ち着いて集中して指導を受けられるよう、環境が整えられた専用の教室です。一方、必要に応じて通常の教室でも指導が行われることがあります。
通級指導の教員

通級指導を担当する教員には、発達障害に関する専門性が求められています。ここでは、通級指導教員の資格や役割について解説します。
通級指導教員の資格
通級指導教員に特別な資格は法的に定められていませんが、多くの教員が特別支援学校教諭免許状を有しています。この免許を持つことで、発達障害の理解と適切な指導方法を身につけることができます。
また、教職経験や特別支援教育に関する研修を重ねることで、通級指導の専門性を高めていく教員も多くいます。
通級指導教員の役割
通級指導教員の主な役割は以下の通りです。
- 児童生徒一人一人の実態の把握
- 個別の教育支援計画や指導計画の作成
- 児童生徒の特性に応じた専門的指導の実施
- 保護者や関係機関との連携
特に、児童生徒の実態を深く理解し、それに基づいた適切な支援を行うことが求められています。また、児童生徒の成長を見守り、継続的な支援体制を整えることも重要な役割です。
通級指導を取り巻く課題

通級指導は発達障害のある児童生徒にとって大きな恩恵をもたらしていますが、一方で課題も存在しています。ここでは通級指導を取り巻く課題について見ていきましょう。
教員不足の問題
近年、通級指導を利用する児童生徒が増加しているため、教員不足が課題となっています。通級指導教員1人が担当する児童生徒数が多すぎて、十分な指導時間が確保できないという指摘があります。
発達障害のある児童生徒一人一人に合わせた適切な指導を行うには、教員の絶対数が不足している状況にあります。行政には、通級指導教員の確保と育成に力を入れることが求められています。
指導の連続性の確保
通級指導を受ける児童生徒にとって、学年が上がるごとに指導内容の連続性が保たれることが重要です。しかし、現状では小学校から中学校、中学校から高校へと進学する際に、支援の連続性が途切れてしまうケースが多いのが実情です。
各学校段階間での適切な引き継ぎや、教員間の連携を強化することで、一貫した支援を提供できるようになることが期待されます。
通常の学級との連携
通級指導教室での指導は、通常の学級での学習を前提としています。したがって、通級指導教員と通常の学級担任との緊密な連携が不可欠となります。
しかし、現場では通常の学級の教員の発達障害への理解が不足していたり、人手不足で十分な連携が取れなかったりする課題があります。通常の学級と通級指導教室がうまく機能し合うよう、教員間の協力体制をさらに強化することが求められています。
まとめ
通級指導は、発達障害のある児童生徒が通常の学級に在籍しながら、専門的な指導を受けられる有益な制度です。児童生徒一人一人の実態に合わせた支援を行うことで、困難の改善や自己肯定感の向上などの効果が期待できます。
一方で、教員不足や支援の連続性の確保、通常の学級との連携などの課題も存在します。行政や学校現場では、通級指導の更なる充実に向けて、これらの課題に真剣に取り組む必要があります。発達障害のある児童生徒が充実した学校生活を送れるよう、通級指導の発展が望まれています。
よくある質問
通級指導の目的は何ですか?
通級指導の主な目的は、発達障害のある児童生徒の学習上や生活上の困難を改善・克服することと、児童生徒の自己肯定感や学習意欲の向上にあります。通常の学級と別室での指導を組み合わせることで、一人一人のニーズに合った適切な支援が実現できます。また、通級指導を受けることで、児童生徒は通常の学級での学習や生活に円滑に参加できるようになります。
通級指導の対象となる発達障害にはどのようなものがありますか?
通級指導の対象となる主な発達障害には、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)などが含まれます。発達障害の程度によって、通級指導の利用の可否が判断されます。比較的軽度の発達障害のある児童生徒が対象となる傾向にあります。
通級指導教員の資格や役割はどのようなものですか?
通級指導教員に特別な資格は法的に定められていませんが、多くの教員が特別支援学校教諭免許状を有しています。この免許を持つことで、発達障害の理解と適切な指導方法を身につけることができます。主な役割は、児童生徒一人一人の実態の把握、個別の教育支援計画や指導計画の作成、児童生徒の特性に応じた専門的指導の実施、保護者や関係機関との連携などです。
通級指導を取り巻く課題にはどのようなものがありますか?
通級指導を取り巻く課題には、教員不足の問題、指導の連続性の確保、通常の学級との連携などがあります。教員不足により、通級指導教員一人が担当する児童生徒数が多すぎて十分な指導時間が確保できないという指摘があります。また、学校段階間での適切な引き継ぎや教員間の連携強化が課題となっています。さらに、通常の学級の教員の発達障害への理解不足や人手不足によって、十分な連携が取れないことも問題となっています。


