はじめに
発達障害のある子どもたちは、気持ちの切り替えが難しいという共通の特徴を持っています。今回は、この課題について深く理解し、適切な対応方法を探っていきます。発達障害の子どもたちが日常生活で直面する具体的な困難と、保護者や周囲の大人ができる支援の方法を、多角的に検証していきましょう。
気持ちの切り替えが難しい理由

発達障害のある子どもが気持ちの切り替えに苦労する理由は、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは、その主な原因について解説します。
見通しを持つことが難しい
発達障害のある子どもは、状況の変化を予測するのが苦手です。次に何が起こるのかが分からないため、現在の活動から新しい活動へ移行することに強い不安を感じてしまいます。このような見通し力の弱さが、気持ちの切り替えを阻害する大きな要因となっています。
例えば、楽しい遊びから宿題に切り替える際、子どもは「遊びがもう終わってしまうのか」と不安になり、なかなか気持ちを切り替えられません。このように、見通しを持てないことが気持ちの切り替えを難しくさせているのです。
こだわりが強い
発達障害のある子どもは、特定の興味関心にとらわれる傾向が強く、それ以外のことに関心を移すのが難しい特性があります。自分の好きなことに熱中し、それを中断させられると激しく反発してしまうのです。
例えば、大好きなゲームをしている最中に次の活動に移行しようとすると、子どもは強く拒否する行動に出ることがあります。こうしたこだわりの強さも、気持ちの切り替えを阻害する一因となっています。
感情のコントロールが苦手
発達障害のある子どもは、感情を上手く制御することが難しいケースが多くみられます。感情が高ぶると、理性的な判断ができなくなり、気持ちを切り替えることがさらに困難になってしまうのです。
不安やストレスを感じた時に、子どもが大きな感情の動揺を経験すると、それまでの活動から気持ちを切り替えて次の課題に取り組むことができなくなります。このような感情のコントロール力の弱さも、大きな要因の一つです。
気持ちの切り替えをサポートする方法

発達障害のある子どもたちの特性を理解した上で、気持ちの切り替えをスムーズに行えるよう、保護者や教師がどのような支援ができるか、具体的な方法をご紹介します。
見通しを持たせる工夫
発達障害のある子どもに、予定の変更を事前に知らせたり、次の活動内容を分かりやすく伝えたりするなど、見通しを持たせる工夫が有効です。具体的には、視覚的な手がかり(スケジュール表やイラスト付きのチェックリストなど)を活用したり、子どもの様子を見ながら口頭で丁寧に説明したりするのがよいでしょう。
このように次の活動内容を把握できれば、子どもは新しい活動への不安を少しずつ和らげることができ、気持ちの切り替えもスムーズになります。
終了時間を事前に知らせる
子どもが夢中になっている活動の終了時間を、あらかじめ分かりやすく伝えておくことで、切り替えへの準備ができます。例えば、「あと10分でゲーム終了ね」といった具合に、終了の目安を伝えます。さらに終了5分前に再度知らせれば、徐々に気持ちの切り替えができるようになるでしょう。
終了時間を知らせることで、子どもは活動に対する見通しを持てるようになり、スムーズな切り替えへとつながります。
上手く切り替えた時は褒める
子どもが上手く気持ちを切り替えられた時は、しっかりと褒め称えることが大切です。小さな成功体験を重ねることで、次第に切り替える力がついていきます。
例えば「宿題に集中できたね。よく頑張った!」と具体的に褒めると、子どもは自信がつきます。このように適切な言葉がけを心がけると、子どもは気持ちの切り替えに対する自信を深めることができるのです。
落ち着く時間を設ける
発達障害のある子どもは、興奮した気持ちを自分で落ち着かせることが難しいことがあります。そのため、活動を切り替える際に、一定の休憩時間を設けることで、子どもが気持ちを切り替えやすくなります。
具体的には、好きな活動から離れてひとりで過ごせる場所を用意したり、軽く体を動かして気分転換をするなど、子どもなりに気持ちを落ち着かせる時間を作ることが大切です。こうした配慮があれば、気持ちの切り替えもスムーズに行えるはずです。
家庭での実践事例

ここまでで気持ちの切り替えの難しさとその対処法について解説してきました。それでは実際に、発達障害のある子どもを持つ保護者の方々はどのような工夫をしているのでしょうか。実際の事例をご紹介します。
スケジュール表の活用
「朝の支度でいつも時間がかかってしまう」といった課題を抱える家庭では、視覚的なスケジュール表の活用が有効です。行う順序と所要時間を示したスケジュールを、目に付く場所に掲示しておきます。
そうすれば子どもは次の活動を把握しやすくなり、気持ちの切り替えも円滑にできるようになります。スケジュール表はオーダーメイドで作成するのがベストですが、インターネットで無料で入手できるものもたくさんあります。発達障害のある子どもにとって、視覚的な手がかりはとても重要な役割を果たすのです。
時間を区切った活動設定
同じ活動を長時間続けると、発達障害のある子どもはなかなかその活動から離れられなくなります。そこで、最初から一定の時間区切りを設定し、短い時間で活動を切り替えることを意識づけるのがポイントです。
例えば、朝の過ごし方を「15分で朝食」「30分で自由時間」「15分で歯磨き・洗面」と区切るなどです。この方法は習慣づけるのに少し時間がかかるかもしれませんが、見通しを持った活動の区切りができるので、徐々に気持ちの切り替えが上手くいくようになります。
学校での実践例
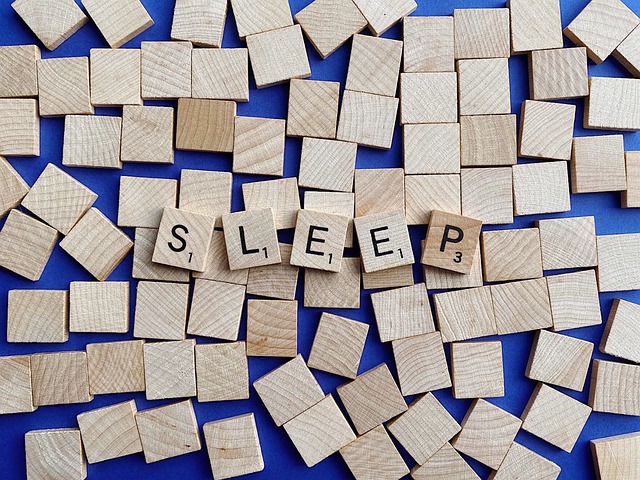
発達障害のある子どもに対しては、家庭だけでなく学校現場でも適切な支援が求められます。気持ちの切り替えをスムーズにするための工夫について、先生方の実践例を見ていきましょう。
切り替え時のルーティン作り
発達障害のある子どもは、決まったルーティンを守ることで次の活動への切り替えを助けることができます。例えば、休み時間の終わりには必ず同じ音楽を流して知らせるなど、ルーティン化された合図があると子どもは次の活動への切り替えが容易になるのです。
また、休み時間と授業の切り替え時には、教師が子どもたち一人一人に声をかけて次の活動への意識づけを行う方法もあります。このようにして、子どもたちに次の活動への「037;気づき」を促すのが大切なポイントなのです。
事前の練習と振り返り
子どもの集中力が切れやすい時間帯の授業では、一つの活動が長く続くと気持ちの切り替えが難しくなります。そこで授業の前に、切り替えの練習と振り返りを行うのが効果的です。
例えば、最初に10分間集中して課題に取り組み、その後休憩を入れて切り替えを行う、といった流れを作ります。休憩明けには子どもたちに「先ほどの課題はどうだったか」と振り返らせ、次の活動への意識づけを促します。こうした機会を重ねることで、子どもたちは徐々に気持ちの切り替えを習得していくのです。
五感を使った気分転換
発達障害のある子どもは、気持ちが高ぶった時に自分で気分転換することが難しい場合があります。そこで、五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)に働きかける手立てを取り入れると効果的です。
例えば、静かな音楽を流したり、香りのする石けんを使ったり、手触りの良い布地に触れさせたりするなどの工夫があります。五感に変化を与えることで、子どもの気持ちを落ち着かせ、次の活動への切り替えをサポートできるのです。
| 五感 | 気分転換の方法例 |
|---|---|
| 視覚 | 落ち着いた色の物を見せる、自然の映像を見せる |
| 聴覚 | 静かな音楽を流す、自然の音を聞かせる |
| 嗅覚 | 香りのするアロマを使用する |
| 触覚 | 手触りの良い布や粘土に触れさせる |
| 味覚 | 好みの飲み物を飲ませる |
まとめ
発達障害のある子どもにとって、気持ちの切り替えは非常に大きな課題となります。しかし、子どもの特性を理解し、見通しを持たせる工夫や切り替え時のサポートを行えば、少しずつ上手に気持ちを切り替えられるようになっていきます。
家庭や学校現場での実践例からも分かるように、子どもへの寄り添い方や支援の仕方を工夫することが何より大切なのです。温かく受容的な態度で子どもと向き合い、一緒に乗り越えていくことが、気持ちの切り替えを身につけさせる上での鍵となるでしょう。
よくある質問
発達障害のある子どもが気持ちの切り替えに苦労する理由は何ですか?
発達障害のある子どもは、状況の変化を予測するのが苦手であり、特定の興味関心にとらわれる傾向が強いため、新しい活動に移行することが困難です。また、感情のコントロールが苦手で、不安やストレスを感じると理性的な判断ができなくなるため、気持ちの切り替えが難しくなっています。
発達障害のある子どもの気持ちの切り替えをサポートするには、どのような方法がありますか?
子どもの次の活動内容を事前に伝えたり、終了時間を知らせたりするなど、見通しを持たせる工夫が有効です。また、上手く切り替えられた時に褒めることで自信につなげたり、一定の休憩時間を設けることで気持ちを落ち着かせることができます。
家庭では、子どもの気持ちの切り替えをどのように支援していますか?
視覚的なスケジュール表の活用や、活動の時間を区切ることで、子どもに見通しを持たせることができます。このような工夫により、徐々に気持ちの切り替えが上手くいくようになっています。
学校現場では、子どもの気持ちの切り替えをどのように支援していますか?
休み時間と授業の切り替え時に、ルーティン化された合図を設けたり、一人一人に声をかけて次の活動への意識づけを行ったりすることで、切り替えをサポートしています。また、授業前に切り替えの練習と振り返りを行ったり、五感を使った気分転換の方法を取り入れたりしています。


