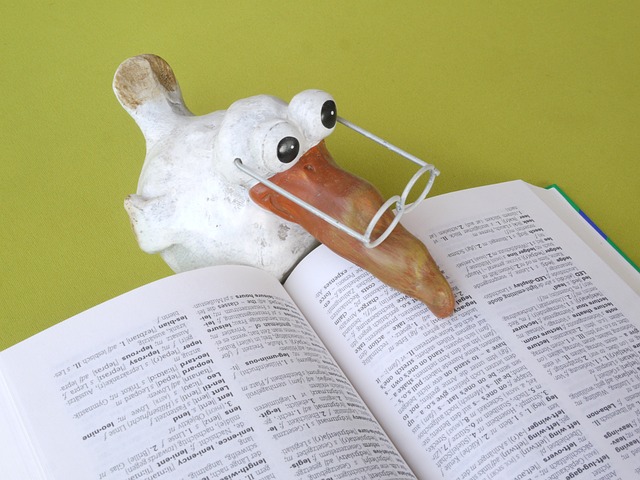はじめに
発達障害は、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、学習障害などを含む、幅広い発達の偏りを指します。発達障害のある人は、コミュニケーションや対人関係、集中力や impulse制御などに困難を抱えることがあります。しかし、適切な支援を受けることで、発達障害のある人も健やかに成長し、社会参加が可能になります。本記事では、発達障害者支援に係る行政の取り組みについて、各セクションでより詳しく解説します。
国の施策と法的枠組み

発達障害者支援は、国を挙げての重要課題となっています。国は、発達障害者支援法を制定し、支援の総合的な推進に取り組んでいます。
発達障害者支援法の概要
発達障害者支援法は、2005年に施行された法律です。この法律は、発達障害者の自立と社会参加の支援を目的としています。国や地方公共団体は、発達障害者の早期発見・早期支援、切れ目のない一貫した支援、社会的障壁の除去などに努める責務を負っています。
発達障害者支援法は、発達障害者の意思決定を尊重し、社会参加を促進することを基本理念としています。また、国民一人ひとりが発達障害への理解を深め、発達障害者の自立と社会参加に協力することが求められています。
発達障害者支援センター
発達障害者支援法に基づき、都道府県や指定都市に発達障害者支援センターが設置されています。このセンターは、発達障害者やその家族に対して、相談支援、発達支援、就労支援、情報提供などを行う重要な拠点です。
| 主な支援内容 | 説明 |
|---|---|
| 相談支援 | 発達障害者やその家族からの様々な相談に応じる |
| 発達支援 | 発達障害児への療育支援や生活支援を提供する |
| 就労支援 | 発達障害者の就労に向けた準備やマッチング、定着支援を行う |
| 情報提供 | 発達障害に関する最新の情報やサービスを提供する |
教育と医療の連携強化
国は、発達障害児への切れ目のない支援を実現するため、教育と医療の連携強化にも取り組んでいます。例えば、医療従事者への発達障害対応力向上研修や、発達障害専門医療機関の初診待機解消事業などが行われています。
また、巡回支援専門員による保育所や放課後児童クラブへの巡回支援、発達障害児者およびその家族に対するピアサポートなどの取り組みも進められています。
地方公共団体の取り組み

発達障害者支援法では、国だけでなく、地方公共団体にも様々な責務が課されています。各自治体は、地域の実情に合わせた独自の取り組みを展開しています。
都道府県の役割
都道府県は、発達障害者支援センターの設置や運営、市町村への技術的支援などを担っています。例えば、宮城県では三次支援機関である発達障害者支援センターが、地域の支援機関とネットワークを構築し、重層的な支援体制を整備しています。
また、福岡県では発達障がい者支援拠点病院を九州大学病院に指定し、医療面での支援を強化しています。さらに、県北部と県南部に療育支援事業所を設置し、ライフステージに応じた療育指導や相談を提供しています。
市区町村の役割
発達障害者支援の最前線は、市区町村にあります。市区町村は、保護者への情報提供、発達支援サービスの利用促進、保育や教育の場での配慮など、発達障害児の早期発見と適切な支援を行う義務があります。
例えば、大阪市発達障がい者支援センター「エルムおおさか」では、発達障がいのある方やその家族への各種相談対応、関係機関への啓発・研修、専門療育機関や就労支援事業などを行っています。また、札幌市では「札幌市発達障がい者支援体制整備事業」を実施し、乳児期から成人期までの一貫した支援を提供しています。
情報提供と理解促進
自治体は、発達障がいに関する正しい理解を促進するため、様々な情報提供に努めています。大阪市内では、発達障がいの診断を行う医療機関のリストが公開されており、大阪府のホームページにも医療機関ネットワークの情報が掲載されています。
また、札幌市では作品展示やパネル展「カラフルブレイン札幌」を開催し、発達障がいへの理解を深める取り組みを行っています。
支援サービスの提供

発達障害のある人は、障害者総合支援法と児童福祉法に基づいて、様々な支援サービスを受けることができます。各自治体の窓口で手続きを行うことで、必要なサービスを利用できます。
成人の発達障害者へのサービス
- 自立支援給付(居宅介護、生活介護、就労移行支援など)
- 地域生活支援事業(相談支援、コミュニケーション支援など)
成人の発達障害者には、自立した生活や就労の支援を目的としたサービスが提供されます。障害者手帳の有無に関わらず、必要性が認められれば利用できます。
児童の発達障害者へのサービス
- 障害児通所支援(児童発達支援、放課後デイサービスなど)
- 障害児入所支援(福祉型障害児入所施設など)
- 短期入所
児童の発達障害者には、成長に合わせた療育支援や施設入所、一時的な預かりなどのサービスが用意されています。保護者の経済的負担も考慮され、所得に応じた利用料設定となっています。
サービス利用の手続き
発達障害福祉サービスを利用するには、市区町村の窓口で以下の手続きを行います。
- 障害支援区分の認定申請
- サービス等利用計画書の作成
- 支給決定
窓口では、必要なサービスの説明や申請手続きの支援を受けることができます。発達障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、まずは相談することが重要です。
就労支援と社会参加

発達障害者の自立と社会参加を促進するため、行政は就労支援や社会生活支援にも力を入れています。
ハローワークでの就労支援
発達障害者の就職や職場定着を支援するため、ハローワークに専門のサポーターが配置されています。発達障害者一人ひとりの特性に応じた、きめ細かな支援を提供しています。
- 求職登録時の相談対応
- 職場実習やジョブコーチ派遣
- 職場への理解促進
- 定着支援
就職後も継続的な支援を受けられるため、発達障害者の方々も安心して就労できます。
コミュニケーション支援の取り組み
発達障害のある人とのコミュニケーションを円滑にするため、公共施設にコミュニケーションボードが設置されています。大阪市では、Osaka Metroの全駅やシティバス、歴史博物館、公園などにボードが備え付けられています。
また、国土交通省から発達障害のある方とのコミュニケーションに関するハンドブックも提供されています。さまざまな場面でのコミュニケーション支援が進められています。
障害者スポーツの振興
発達障害のある人の社会参加を後押しするため、障害者スポーツの推進も重要な取り組みです。行政は、障害者スポーツ大会の開催や施設整備、指導者の育成など、障害者スポーツの振興に尽力しています。
スポーツを通じて健康増進を図るだけでなく、発達障害のある人の自信や可能性を広げることにもつながります。地域で障害者スポーツが盛んになれば、発達障害への理解も深まるでしょう。
まとめ
発達障害者支援は、国を挙げての重要課題となっています。国は法的枠組みを整備し、地方公共団体と連携しながら、発達障害者の自立と社会参加に向けた総合的な支援を行っています。各自治体でも、地域の実情に合わせた様々な取り組みが展開されています。
発達障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、発達支援から就労支援、医療、教育など、ライフステージに応じた切れ目のない支援体制の構築が求められています。行政の施策とともに、国民一人ひとりが発達障害への理解を深め、発達障害者の社会参加を後押しすることが重要です。
よくある質問
発達障害とはどのようなものですか?
発達障害は、自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動性障害、学習障害などを含む幅広い発達の偏りを指します。発達障害のある人はコミュニケーションや対人関係、集中力や impulse制御などに困難を抱えることがありますが、適切な支援を受けることで健やかに成長し、社会参加が可能になります。
発達障害者支援の法的枠組みはどのようなものですか?
発達障害者支援法が2005年に施行され、発達障害者の自立と社会参加の支援を目的としています。国や地方公共団体には発達障害者の早期発見・早期支援、切れ目のない一貫した支援、社会的障壁の除去などの責務が課されています。また、発達障害者の意思決定を尊重し、社会参加を促進することが基本理念とされています。
発達障害者支援センターの役割は何ですか?
発達障害者支援法に基づき、都道府県や指定都市に設置された発達障害者支援センターは、発達障害者やその家族に対して、相談支援、発達支援、就労支援、情報提供などを行う重要な拠点です。医療や教育との連携を通じて、発達障害者の自立と社会参加を支援しています。
発達障害者に対するサービスにはどのようなものがありますか?
成人の発達障害者には、自立した生活や就労を支援するためのサービスが提供されます。児童の発達障害者には、成長に合わせた療育支援や施設入所、一時預かりなどのサービスが用意されています。これらのサービスは、市区町村の窓口で申請・利用手続きを行うことができます。