はじめに
発達障害は、脳機能の障害によって引き起こされる障害で、さまざまな特徴があります。発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの下位分類がありますが、どの発達障害にも共通する特徴もあれば、個別の症状もあります。発達障害のある人は、コミュニケーションや対人関係、行動面での困難さを抱えることが多く、早期発見と適切な支援が重要です。この記事では、発達障害の特徴について詳しく解説していきます。
コミュニケーションと対人関係の困難

発達障害のある人は、コミュニケーションや対人関係に困難を抱えることが多く、これが大きな特徴の一つです。
言葉の発達の遅れ
発達障害のある子どもは、言葉の発達が遅れる傾向にあります。単語の習得が遅れたり、会話の制御が難しかったりします。こうした言葉の発達の遅れは、コミュニケーション能力の発達を阻害し、対人関係に支障をきたす可能性があります。
アスペルガー症候群のある人は、言葉自体は話せるものの、会話のやりとりが上手くできないことがあります。また、文字通りの意味しか理解できず、比喩的な表現を理解するのが難しいです。こうした言葉の発達の特徴により、対人関係がうまくいかないことがあります。
他者の気持ちの理解の難しさ
発達障害のある人は、他者の気持ちを理解することが難しい傾向にあります。相手の表情や気持ちを読み取ったり、自分の行動が相手にどう映るかを考えたりするのが苦手です。そのため、人との関係を上手く築くことが難しくなります。
ASDのある人は、表情の変化や非言語的な手がかりを読み取ることが苦手です。また、自分と他者の気持ちを区別するのも困難を伴います。このため、相手の気持ちを汲み取り、適切な対応をすることが難しくなります。
社会的なルールの理解の難しさ
発達障害のある人は、社会的なルールや慣習を理解するのが難しいことがあります。人との付き合い方や、場面に応じた適切な行動がわからず、いわゆる「空気が読めない」状況に陥りがちです。
このように、発達障害には様々な特徴がありますが、コミュニケーションと対人関係の困難さは共通する大きな特徴の一つです。支援の際にはこの点に留意し、個別の特性に合わせた対応が重要になります。
こだわりや興味関心の偏り

発達障害のある人は、特定のものやことに強いこだわりを示したり、興味関心が偏ったりする傾向があります。
同じパターンの行動の繰り返し
発達障害のある人は、同じパターンの行動を繰り返しがちです。例えば、毎日同じ服を着たり、同じ道順で歩いたりするといった具合です。このようなこだわりは、環境の変化に強い不安を抱くためです。
自閉症のある子どもの中には、物を線路状に並べたり、指をくるくると回したりする傾向がみられることがあります。このような行動は、不安を和らげるための拗れだと考えられています。
特定の話題への強いこだわり
発達障害のある人は、特定の話題に強いこだわりを示すことがあります。例えば、電車の種類や路線について熱心に話したり、恐竜の名前や大きさなどを詳しく説明したりするかもしれません。
こうした特定の話題へのこだわりは、ASDに特徴的な傾向です。ASDのある人は、関心のあることについては驚くほど詳しい知識を持っていますが、興味のない分野については全くの無関心だったりします。
感覚の過敏さや鈍麻さ
発達障害のある人は、感覚の過敏さや鈍麻さを示すことがあります。音や光、匂いに極端に敏感だったり、逆に鈍感だったりするのです。
感覚の過敏さは、環境の変化に強い不安を抱かせます。また、感覚の鈍麻さは、危険を予測できないため、事故につながる恐れがあります。このように、感覚の特性もこだわりの一種と考えられています。
注意欠陥と多動性

発達障害の特徴として、注意欠陥と多動性があります。ADHDではこの傾向が顕著に現れますが、他の発達障害でも同様の特徴がみられることがあります。
集中力の低さ
発達障害のある人は、集中力が続きにくい傾向にあります。ちょっとした刺激にも気が散ってしまったり、長時間同じ作業に取り組むのが難しかったりします。
ADHDのある子どもは特に、授業中に集中できず、よく注意されがちです。しかし、これは本人の意志で集中できないわけではなく、脳の機能障害によるものです。適切な支援があれば、集中力を高めることができます。
多動性と衝動性
発達障害のある人は、落ち着きがなく、多動になったり、衝動的な行動をとったりする傾向があります。ADHDの症状としてよく知られていますが、他の発達障害でも同様の特徴がみられます。
多動性は、いつまでも座っていられずに動き回ってしまう傾向のことです。衝動性は、考えずに行動してしまうことを指します。こうした症状は、周囲に迷惑をかけてしまうこともあります。しかし、本人への適切な指導と理解があれば、改善が期待できます。
学習面での困難
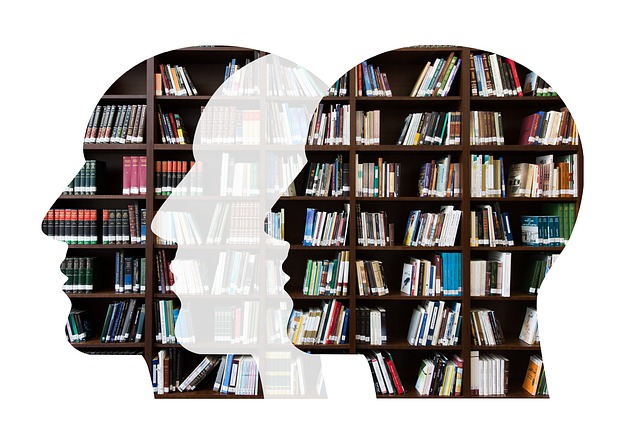
発達障害には、読み書きや計算、推論など、学習の特定の分野で困難を示す特徴があります。
読み書きの困難
発達障害のある人は、読み書きに著しい困難を示すことがあります。文字の認識が苦手だったり、文章の意味を理解できなかったりします。
この症状は、「dyslexia」と呼ばれる学習障害の一種です。早期発見と適切な支援があれば、読み書きの能力を伸ばすことができます。例えば、文字を大きく印刷したり、音声教材を活用したりする工夫が有効です。
計算の困難
発達障害のある人は、計算が苦手な傾向にあります。数の概念を理解するのが難しかったり、筆算の方法がわからなかったりすることがあります。
この症状は、「dyscalculia」と呼ばれる学習障害の一種です。早期発見と適切な支援が重要で、例えば、具体物を用いた算数指導や、計算アプリの活用などが有効な手段となります。
推論の困難
発達障害のある人は、推論力に乏しい傾向があります。文章の内容から論理的に考えたり、問題の本質を掴んだりするのが苦手です。
論理的思考力の向上は、学習のみならず、社会生活を送る上でも欠かせません。具体的な事例を基に指導したり、視覚的な工夫を取り入れたりすることで、推論力を伸ばすことができます。
併存する症状
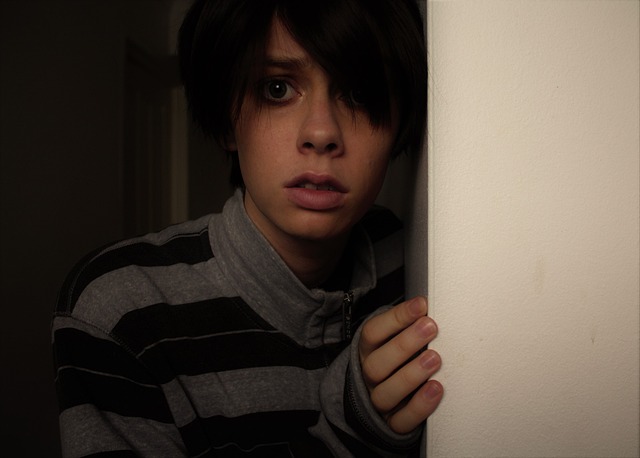
発達障害には、主症状以外にも様々な併存症状があります。これらの症状を理解し、適切に対処することが重要です。
不安やストレス
発達障害のある人は、環境の変化や人間関係にストレスを感じやすい傾向にあります。また、自分の障害に気づいていると、将来への不安を抱えがちです。
不安やストレスが高じると、パニック発作を起こしたり、自傷行為に走ったりするなど、深刻な事態に発展する恐れがあります。本人の精神面のケアと、周囲の理解が不可欠です。
うつ病や不登校
発達障害のある人は、うつ病や不登校に陥りがちです。友人関係の構築が困難だったり、学業で悩みを抱えたりするために、心理的なストレスが高まるためです。
この症状に対しては、カウンセリングや環境調整、必要に応じた薬物療法などの支援が有効です。また、家族や教師、医療機関などが連携し、本人を温かく見守ることが欠かせません。
チックやてんかん
発達障害には、チックやてんかんなどの運動障害が併存することがあります。チックは不随意な運動や音声で表れ、てんかんは意識障害を伴う発作を起こします。
チックには、ストレスが関係していることが多いため、ストレス対策が重要です。てんかんの発作は、突発的に起きるため、周囲の理解と適切な対処法を身につける必要があります。
まとめ
発達障害には、コミュニケーションや対人関係の困難、こだわりや興味関心の偏り、注意欠陥や多動性、学習面での困難など、様々な特徴があります。また、不安やうつ、チックなどの併存症状も見られます。
発達障害の特徴は一人ひとり異なり、年齢や環境によっても変化します。そのため、個別の特性を理解し、本人に合った支援を行うことが重要です。早期発見と適切な療育、周囲の理解が、発達障害のある人の社会参加と自立を後押ししていくのです。
よくある質問
発達障害の特徴は何ですか?
発達障害の主な特徴は、コミュニケーションや対人関係の困難、こだわりや興味関心の偏り、注意欠陥や多動性、学習面での困難などです。また、不安やうつ、チックなどの併存症状も見られます。
発達障害の人はどのようにサポートされるべきですか?
発達障害の特徴は一人ひとり異なり、年齢や環境によっても変化するため、個別の特性を理解し、本人に合った支援を行うことが重要です。早期発見と適切な療育、周囲の理解が、発達障害のある人の社会参加と自立を後押ししていきます。
発達障害と併存する症状には何があるのですか?
発達障害には、不安やストレス、うつ病、不登校、チックやてんかんなどの併存症状がみられます。これらの症状を理解し、適切に対処することが重要です。
発達障害の原因は何ですか?
発達障害は、脳機能の障害によって引き起こされる障害で、さまざまな特徴があります。遺伝的な要因や環境要因などが関係していると考えられています。


