はじめに
発達障害のある子どもの中には不登校になる子が少なくありません。発達障害の特性、例えばコミュニケーション能力の低さや感情コントロールの難しさなどが、学校生活に大きな影響を及ぼしている可能性があります。不登校の背景には発達障害が関係していることが多く、適切な支援と配慮が必要不可欠です。本記事では、発達障害と不登校の関係や、効果的な支援の在り方について詳しく解説していきます。
発達障害と不登校の関係

発達障害のある子どもたちが不登校になる理由は様々です。軽度の発達障害の場合、周囲から理解されにくく、孤立してしまうことがあります。中度や重度の場合は、学習面での困難や衝動性、こだわりなどの特性が、学校生活への適応を難しくしてしまいます。
ASD(自閉症スペクトラム症)とコミュニケーション
ASDの子どもは人とコミュニケーションをとる際の困難さを抱えています。対人関係を構築するのが苦手で、クラスメイトやお友達との会話が続かないことがあります。また、話の受け答えが一方的になりがちで、相手の気持ちを汲み取るのが難しく、孤立してしまう可能性があります。
さらに、些細な環境の変化に強いストレスを感じる特性もあり、学校生活になじめず不登校になってしまうケースがよくみられます。
ADHDと集中力の課題
ADHDの子どもは注意力が散漫になりがちで、授業中に集中し続けるのが困難です。多動性もあり、落ち着いて座っていられないため、授業を妨げてしまうこともあります。また、衝動性から考えずに行動してしまい、トラブルに巻き込まれることもあります。
このような特性から学習の遅れが生じやすく、授業についていけず孤立感を感じてしまいます。さらに、友人関係の構築も難しくなり、不登校につながる可能性が高くなります。
LDと学習面での困難
LDの子どもは、読み書きや計算など、特定の学習面で著しい困難を抱えています。教科書が理解できず、宿題をこなすことができません。言語性や視覚性の認知能力に偏りがあるため、教師の説明を理解するのが難しい場合もあります。
このような苦手分野が重なれば重なるほど、授業についていけなくなり、無力感や劣等感を抱いてしまいます。さらに、友人からからかわれるなど、いじめにもあいやすくなります。そのため、不登校になってしまう子どもが多くなるのです。
不登校への適切な支援と配慮

発達障害のある子どもが不登校になった場合、適切な支援と配慮が欠かせません。発達障害の特性を理解し、子ども一人ひとりにあった支援を行うことが重要です。
家庭での支援
不登校になった子どもには、まず十分な休息と家庭での安らぎが必要です。子どもの気持ちに寄り添い、無理強いせずに休ませることが大切です。子どもの興味関心に合わせて、好きなことを一緒にしたり、外出の機会を設けたりすることで、ストレスを溜めないよう心がけましょう。
また、家庭での学習環境を整えることも重要です。発達障害の特性に合わせて学習方法を工夫したり、生活リズムを乱さないよう気を配ったりすることで、少しずつ学習への意欲を高めていくことができます。
学校との連携
学校との連携は欠かせません。担任の先生や特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラーなどと情報を共有し、子どもの特性と状況を丁寧に説明しましょう。不登校の背景を話し合い、学校復帰に向けた段階的な計画を立てることが大切です。
また、別室登校や通級指導教室の利用、個別の学習支援など、発達障害の子どもに合った学びの場を確保することも重要です。教師の理解を深め、合理的配慮を求めていく必要があります。
専門機関の活用
発達障害のある子どもの不登校支援には、医療や福祉の専門機関の力が欠かせません。児童精神科や発達障害者支援センターなどと連携し、子どもの特性の評価や支援プランの作成、ペアレントトレーニングなどを行うことで、適切な支援につなげられます。
また、フリースクールやデイサービス、放課後等デイサービスなどの利用も検討すべきでしょう。発達障害に理解のあるスタッフに囲まれ、障害特性に応じた学習支援や生活訓練、余暇活動などを受けられる機会があります。
学校現場の課題と必要な対応
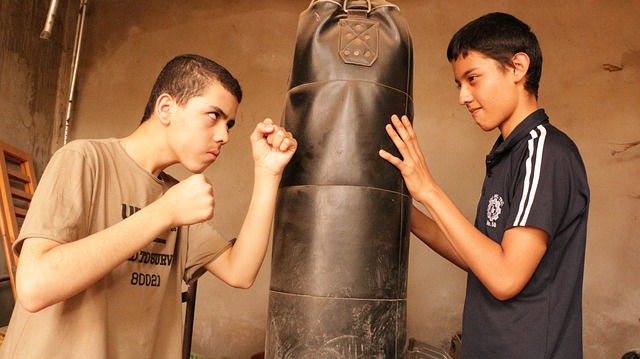
学校現場においても、発達障害のある子どもの支援には課題が残されています。教員の理解不足や体制の不備から、適切な支援が行き渡っていないのが現状です。
教員の発達障害理解の推進
教員が発達障害の特性を正しく理解することが大前提となります。発達障害は見た目には分かりにくい障害なので、子どもの行動の背景にある特性に気づくことが難しい場合があります。そのため、教職課程や現職研修で発達障害に関する知識を深める必要があります。
特に通常学級に在籍する発達障害の子どもへの合理的配慮は欠かせません。一人ひとりの特性に応じた指導方法や学習環境の調整、支援の仕方など、きめ細かな対応が求められます。
校内支援体制の強化
学校全体で発達障害のある子どもを支援する体制づくりが不可欠です。特別支援教育コーディネーターを中心に、管理職、普通学級の教員、特別支援学級の教員、スクールカウンセラーなどが連携し、一貫した支援を行う必要があります。
また、通級指導教室の拡充や支援員の配置、別室の確保など、ハード面での環境整備も重要です。発達障害のある子どもが落ち着いて学べる場所を確保し、ニーズに合わせた指導を受けられるようにすることが大切です。
地域と連携した支援の推進
学校だけでなく、地域全体で発達障害のある子どもを支援する体制を整える必要があります。教育委員会、医療機関、児童相談所、NPO法人などが連携し、切れ目のない支援を提供することが理想的です。
また、発達障害への理解を深めるため、地域住民への啓発活動も欠かせません。偏見をなくし、発達障害のある子どもが地域で受け入れられるよう、様々な機会をとらえて発信していくことが重要です。
フリースクールの取り組み
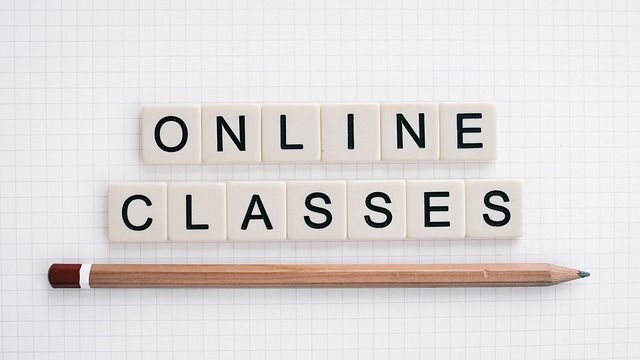
不登校の子どもたちの居場所として、フリースクールの役割が注目されています。発達障害のある子どもたちも、その特性に合わせた学習支援や生活支援を受けられるケースが増えてきました。
学習支援と個別対応
フリースクールでは、子どもたちの実態に合わせた学習支援が行われています。基礎学力の定着から、進路選択の相談までサポートされます。ADHDの子どもには、集中力を高める工夫がされたり、LDの子どもには視覚教材を使った指導が行われたりするなど、一人ひとりに合わせた配慮がされています。
また、発達障害の特性から生じるコミュニケーションの難しさにも対応しています。個別の学習スペースが用意されたり、スタッフによる細かな対応がなされたりすることで、子どもたちが安心して学べる環境が整えられています。
生活支援と余暇活動
フリースクールでは学習支援だけでなく、生活面でのサポートも行われています。発達障害のある子どもにとって、生活リズムを維持することは大切な課題です。スタッフが生活リズムの立て直しを手伝ったり、家事や身辺自立を促したりするなど、社会生活に必要なスキルを身につける機会が提供されています。
さらに、スポーツ、音楽、アウトドア活動など、趣味や特技を伸ばす余暇活動のプログラムも用意されています。発達障害の特性から生じがちな自己否定感を払拭し、自信を持てるよう、居場所作りと自己実現の場が提供されているのです。
専門スタッフと地域連携
フリースクールには発達障害の分野に詳しい専門スタッフが在籍しているところが多くあります。教員免許や心理カウンセラーの資格を持つ者のほか、大学生ボランティアなども支援に携わっています。このように専門性が高いことが、発達障害の子どもへの適切な支援につながっています。
さらに、地域の専門機関とも連携しながら支援を行っています。児童相談所や障害者就労支援センターなどと協力し、子ども一人ひとりに合った進路選択のアドバイスや就労支援を行うなど、切れ目のない支援体制が整備されつつあります。
個別のケースと親の体験談

発達障害のある子どもの不登校支援には、一人ひとりの事情に応じた対応が重要です。以下では、実際の事例と親御さんたちの体験談を紹介します。
ASDの長男の不登校
ASDの特性から対人関係に困難を抱えていた長男は、中学2年生の時に不登校になりました。いじめが原因だったようですが、教師の理解が足りず、適切な支援を受けられませんでした。学校とのやりとりに疲れ果て、家に引きこもるようになってしまいました。
母親は専門家に相談し、発達障害について学びました。そして長男の特性を理解し、無理強いせずに受け入れることが大切だと気づきました。母子で信頼関係を作り直し、長男のペースに合わせながら、フリースクールの利用や公園での散歩などを通して、外に出る機会を設けていきました。2年がかりで徐々に改善し、高校受験にもこぎ着けました。
ADHDの次男の別室登校の課題
ADHDの次男は4年生から別室登校となりましたが、自信を失い、ほとんど自習するだけになってしまいました。教員の手が足りず、適切な指導を受けられなかったのです。5年生になると給食時間のみ登校し、2週間休み続けるようになりました。
母親は、先生の「物事がこうあるべき」という固定観念が、子どもにとって過酷すぎると感じていました。別室登校では孤立し、支援が行き届かない実態がありました。そこで近くの療育センターを利用し、発達障害の特性に合わせた学習支援を受けるようにしました。そうして徐々に学習意欲が戻り、小学校を無事に卒業できました。
アスペルガー傾向の浅井さんの中高生時代
浅井真子さんは小学校から中学にかけて、アスペルガー症候群の傾向と高い知的能力を併せ持っていました。しかし、教師の理解不足から適切な支援が受けられず、不登校になってしまいました。
母親は粘り強く学校に働きかけ、理解を求めましたが、なかなか前に進みませんでした。そこで民間の学習塾に通わせたり、家庭教師をつけたりするなどして、浅井さん自身の学習意欲を維持するよう努めました。高校受験に向けて不登校は解消されましたが、中学時代は大変な思いをしたそうです。
まとめ
発達障害のある子どもが不登校になるケースは珍しくありません。学校生活に伴うさまざまな困難が原因となっており、子どもの特性に合わせた支援が欠かせません。家庭では子どもの気持ちに耳を傾け、ストレスを溜めさせないよう配慮する必要があります。また、学校と連携しながら、個別の学習支援や環境調整を行っていくことが重要です。さらに、専門機関の助言を仰ぎ、フリースクールなどの活用も検討すべきでしょう。
学校現場では、教員の発達障害理解を深め、校内支援体制を強化していくことが求められます。地域でも、発達障害への理解促進と支援体制の整備が急がれます。発達障害のある子どもの不登校は、家庭・学校・地域が連携し、切れ目のない支援を行うことで改善が期待できます。一人ひとりの特性に合わせた、きめ細かな支援が何より大切なのです。
よくある質問
発達障害のある子どもが不登校になる理由は何ですか?
発達障害の特性、例えばコミュニケーション能力の低さや感情コントロールの難しさから、学校生活への適応が難しくなり、孤立感や無力感を感じて不登校になることが多いです。また、学習面での困難から授業についていけず、いじめにあいやすくなることも理由とされています。
発達障害のある子どもの不登校をどのように支援すればよいですか?
家庭では子どもの特性に合わせた学習環境の整備や生活リズムの調整、学校とも連携しながら子どもの実情に応じた支援計画を立てることが大切です。また、医療や福祉の専門機関と協力し、発達障害の評価や適切な支援につなげることも重要です。
学校現場では発達障害のある子どもの支援にどのような課題があるのですか?
教員の発達障害に関する理解不足や校内支援体制の不備から、適切な支援が十分に行き渡っていないのが現状です。教員研修の充実や校内体制の強化、地域との連携強化が求められます。
フリースクールはどのように発達障害のある子どもを支援しているのですか?
フリースクールでは、一人ひとりの特性に合わせた学習支援や生活リズムの立て直し、余暇活動などを通して、発達障害のある子どもの居場所作りと自己実現の機会を提供しています。また、専門性の高いスタッフが地域の専門機関と連携しながら、切れ目のない支援を行っています。


