はじめに
注意欠陥多動性障害(ADHD)は、不注意、多動性、衝動性を主な症状とする神経発達障害です。ADHDの症状は子供のころから現れ、成人期にも継続することがあります。本記事では、ADHDの原因や症状、診断方法、治療法など、ADHDに関する様々な側面を詳しく解説していきます。
ADHDとは
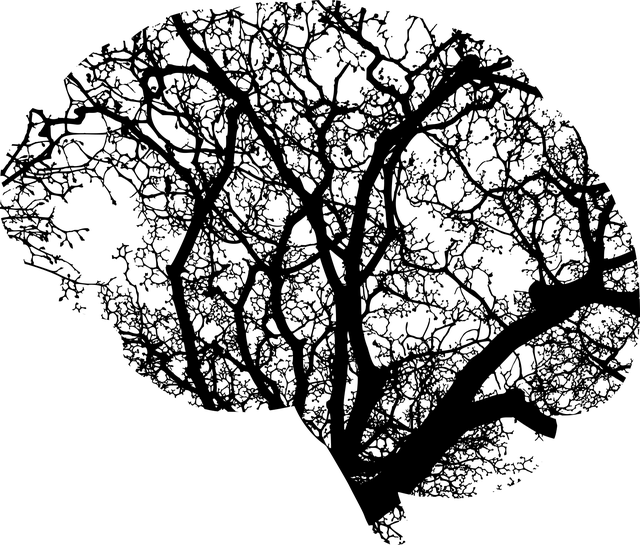
ADHDは、注意力の欠如、過剰な活動性、衝動的な行動を特徴とする神経発達障害です。ADHDの症状は個人差が大きく、年齢や環境によっても変化します。
症状
ADHDの主な症状には、以下のようなものがあります。
- 不注意:集中力が続かず、細かい作業を避ける傾向がある
- 多動性:落ち着きがなく、しょっちゅう動き回る
- 衝動性:つい口をはさんでしまったり、順番を待てない
これらの症状は、学業や対人関係、日常生活に支障をきたすことがあります。また、ADHDの症状は幼児期から現れますが、年齢とともに変化していきます。例えば、多動性は年齢とともに改善する傾向にありますが、不注意の症状は成人期まで続くことが多いです。
原因
ADHDの原因は完全には解明されていませんが、以下のような要因が関係していると考えられています。
- 遺伝的要因:ADHDの親から子へと遺伝する可能性がある
- 脳の機能異常:前頭葉や線条体の機能異常が関与している
- 神経伝達物質の不均衡:ドーパミンやノルアドレナリンの不足が関係する
ADHDの発症には複数の要因が関係しており、単一の原因ではないと考えられています。
ADHDの種類
ADHDは、症状の現れ方によって以下の3つのタイプに分類されます。
- 不注意優勢型:不注意の症状が目立つ
- 多動性-衝動性優勢型:多動性や衝動性の症状が目立つ
- 混合型:不注意、多動性、衝動性の症状がすべて見られる
ADHDの症状は年齢や環境によって変化するため、タイプも変わる可能性があります。
ADHDの診断

ADHDの診断には、専門医による詳しい問診と観察が必要です。診断の際には、以下の点が重視されます。
症状の確認
ADHDの主な症状である不注意、多動性、衝動性が、複数の場面で一貫して見られるかどうかを確認します。症状が12歳までに現れていたかどうかも重要です。
また、ADHDの症状がどの程度の頻度で見られるかを評価するために、さまざまな評価尺度が使用されることがあります。具体的には、コナーズ親評価尺度やADHD症状チェックリストなどです。
他の障害との鑑別
ADHDと類似した症状を示す他の発達障害や精神疾患がないかを慎重に調べる必要があります。例えば、自閉スペクトラム症、学習障害、不安障害、うつ病などとの鑑別が重要です。
ADHDには他の障害が併存していることも多く、その場合は適切な治療が必要となります。
発達歴の聴取
ADHDは生まれつき持っている障害なので、出生時の状況や発達の経過を詳しく確認します。乳幼児期から現在に至るまでの行動の変化を把握することが重要です。
また、家族に ADHDの人がいるかどうかも参考にされます。遺伝的な要因があるためです。
ADHDの治療

ADHDの治療には、薬物療法と心理社会的アプローチの2つがあります。両者を組み合わせて総合的に行うことが一般的です。
薬物療法
ADHDの薬物療法には、主に2種類の薬剤が使用されています。
- メチルフェニデート:ドーパミンやノルアドレナリンの作用を高める中枢神経刺激薬
- アトモキセチン:ノルアドレナリンの再取り込みを阻害する非刺激性薬剤
これらの薬剤は、不注意や多動性、衝動性の症状を改善する効果があります。ただし、副作用にも注意が必要です。
薬物療法は、医師の指導の下で行う必要があり、適切な薬剤と用量を選択することが大切です。また、成長に伴って調整が必要な場合もあります。
心理社会的アプローチ
ADHDの治療では、薬物療法と併せて心理社会的なアプローチも重要視されています。具体的には、以下のような方法があります。
- 行動療法:適切な行動を強化し、問題行動を減らすための技法
- 認知行動療法:考え方や態度を変えることで、行動の改善を図る
- 家族支援:家族への教育や助言を通じて、ADHDの人を支援する
- 学校支援:教師への助言や環境調整を行う
心理社会的アプローチでは、ADHDの人のみならず、家族や教師、周囲の人々にも理解を深めてもらうことが重要です。
ADHDと付随する問題

ADHDの人は、さまざまな二次的な問題に直面することがあります。これらの問題への対応も重要です。
学習面での問題
ADHDの不注意や多動性、衝動性の症状は、学習面での困難をもたらします。具体的には、以下のような問題が起こりやすいです。
- 教師の指示や説明を聞き逃す
- 課題に集中できず、中途半端に終わってしまう
- 忘れ物や落ち着きのなさから、授業に遅刻したり欠席したりする
このような問題に対しては、個別の指導や環境調整、補助具の活用などの支援が有効です。また、ADHDに伴う学習障害への対応も重要となります。
対人関係の問題
ADHDの人は、対人関係においても困難を抱えることがあります。例えば、以下のような問題が起こりやすいです。
- 衝動的な発言や行動で、周りの人を傷つけてしまう
- 順番を守れず、人との折り合いがつけられない
- 気が散りやすく、相手の話を最後まで聞けない
対人関係の問題に対しては、ソーシャルスキルトレーニングなどが有効とされています。また、周りの人々のADHDに対する理解を深めることも大切です。
気分障害や不安障害の併存
ADHDの人は、気分障害(うつ病など)や不安障害を併発しやすいことがわかっています。ADHDに伴う困難から、自尊心が低下したり、ストレスがたまったりすることが原因と考えられています。
気分障害や不安障害が併存する場合は、それぞれに対する治療が必要になります。薬物療法や認知行動療法などが有効とされています。
まとめ
ADHDは、不注意、多動性、衝動性を主症状とする神経発達障害です。症状は個人差が大きく、年齢や環境によっても変化します。ADHDの診断と治療には、専門家による適切なアプローチが重要です。
ADHDの治療には薬物療法と心理社会的アプローチを組み合わせる必要があり、家族や教師、周囲の理解と協力も欠かせません。また、ADHDに付随する二次的な問題にも目を向ける必要があります。
ADHDは一生付き合っていかなければならない障害ですが、適切な支援を受けることで、ADHDの人も健やかに育ち、社会の中で活躍することができます。
よくある質問
ADHDの主な症状は何ですか?
ADHDの主な症状は、不注意、多動性、衝動性です。不注意では集中力が続かず、細かい作業を避ける傾向があります。多動性では落ち着きがなく、しょっちゅう動き回ります。衝動性では、つい口をはさんでしまったり、順番を待てないといった特徴があります。これらの症状は学業や対人関係、日常生活に支障をきたすことがあります。
ADHDの原因は何ですか?
ADHDの原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因、脳の機能異常、神経伝達物質の不均衡などが関係していると考えられています。ADHDの発症には複数の要因が関与しており、単一の原因ではないと考えられています。
ADHDの診断はどのように行われますか?
ADHDの診断には、専門医による詳しい問診と観察が必要です。症状の確認、他の障害との鑑別、発達歴の聴取などを行い、ADHDの主な症状が複数の場面で一貫して見られるかどうかを評価します。また、各種の評価尺度を用いて、症状の程度を詳しく確認することもあります。
ADHDの治療にはどのような方法がありますか?
ADHDの治療には、薬物療法と心理社会的アプローチの2つがあります。薬物療法では、ドーパミンやノルアドレナリンの作用を高める中枢神経刺激薬やノルアドレナリンの再取り込みを阻害する非刺激性薬剤が使用されます。心理社会的アプローチでは、行動療法や認知行動療法、家族支援、学校支援などが行われます。両者を組み合わせて総合的に行うことが一般的です。


