はじめに
ADHDとは、注意欠陥多動性障害のことを指します。この発達障害は、不注意、多動性、衝動性という3つの主な特徴があり、日常生活や学業、社会生活に支障をきたします。本日はADHDについて詳しく解説していきます。
ADHDとは
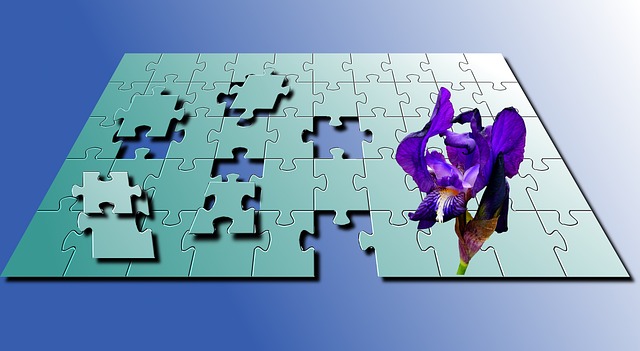
ADHDは、脳の発達の偏りによって起こる神経発達症です。主な症状としては以下の3つが挙げられます。
不注意
ADHDの人は、注意力が持続しにくく、集中力に欠けがちです。細かいミスが目立ち、物を無くしたり忘れ物をしたりしやすいのが特徴です。
例えば、会話の最中に気が散ってしまったり、作業を中断してしまうことが多々あります。また、指示された内容を最後まで聞き逃したりするので、細かい手順を守ることが苦手です。
多動性
ADHDの人は落ち着きがなく、じっとしていることが苦手です。いつも動き回っていたり、しゃべり続けたりすることが多いのが特徴的です。
例えば、座っていても手足を動かし続けたり、適切でない場面で立ち歩いたりします。また、落ち着いた遊びや活動が続かず、次々と新しい活動に移ってしまいます。
衝動性
ADHDの人は思考を制御することが難しく、つい衝動的な行動をしてしまいがちです。順番を待つことや、質問に答える前に待つことが苦手です。
例えば、話し手を遮ってしまったり、授業中に自分の順番ではないのに発言してしまうこともあります。また、危険な行動をすることもあり、事故につながる可能性があります。
ADHDの原因

ADHDの正確な原因はまだ解明されていませんが、以下のようなことが関係していると考えられています。
脳の発達の偏り
ADHDの人の脳では、前頭前野の働きが低下していることが分かっています。前頭前野は注意機能や行動抑制を司る部位なので、その発達の偏りが症状の原因と推測されています。
また、脳内の神経伝達物質である「ドーパミン」と「ノルアドレナリン」の量が少なめであることも指摘されています。これらの物質が不足していると、注意力の維持や行動の制御が困難になります。
遺伝的要因
ADHDには遺伝的な要因が関係していると考えられています。双子研究などから、ADHDの発症リスクが遺伝することが明らかになっています。
ただし、遺伝だけが全ての原因ではありません。環境要因との相互作用が重要であり、遺伝と環境の両方が関与していると推測されています。
環境要因
環境要因の一つとして、出生時や胎内の問題が指摘されています。例えば、低出生体重児や喫煙による影響などが、脳の発達に影響を与えるかもしれません。
また、親の養育態度や家庭環境なども要因の一つと考えられています。ただし、しつけが原因というよりは、環境が症状を助長させる可能性が高いと言えます。
ADHDの症状

ADHDの主症状は、不注意、多動性、衝動性の3つでしたが、実際にはその他にも様々な付随する症状があります。
二次障害
ADHDの人は、上記の3つの症状から様々な二次障害を引き起こしやすいことが知られています。例えば以下のようなものです。
- 学習障害
- 不登校
- いじめの加害者・被害者になりやすい
- うつ病や不安障害
- 反抗挑戦性障害
行動上の問題
不注意や衝動性から、次のような行動上の問題が生じやすいと言われています。
- 約束を守れない
- 時間を守れない
- 整理整頓ができない
- 金銭管理ができない
- ルールを守れない
対人関係の問題
多動性や衝動性から、対人関係でもこのような問題が出やすいとされています。
- 人の話を最後まで聞けない
- 相手の気持ちを踏み越えてしまう
- 発言がコントロールできない
- 感情の制御が難しい
ADHDの診断

ADHDの診断は、医師による様々な検査によって総合的に行われます。主な診断の流れは以下の通りです。
症状の確認
まずは、医師による詳しい問診が行われます。不注意や多動性、衝動性といった症状があるかを確認し、その程度や持続期間なども評価します。
また、ADHDの行動チェックリストなどの評価尺度を使い、症状の有無や程度を客観的に測ることもあります。
発達の確認
次に、これらの症状がいつ頃から現れたのかを確認します。ADHDは小児期からの症状が必要条件なので、幼少期の発達歴を詳しく聞かれます。
また、症状が複数の場面(家庭、学校など)で起きているかも重要なポイントとなります。
除外診断
ADHDの症状は他の障害とも似ているため、最終的にほかの障害やストレス、環境の影響を除外する作業も欠かせません。
例えば、自閉症スペクトラム症、知的障害、ぎょうひひょう性障害、不登校などを見極める必要があります。
ADHDの治療

ADHDの治療は、薬物療法と心理社会的アプローチが組み合わされて行われることが多いです。
薬物療法
ADHDの薬物療法には、以下のような薬が使われます。
- メチルフェニデート系薬剤
- アトモキセチン
- アルファ作動薬
これらの薬は、脳内の神経伝達物質の量を調節することで、不注意や多動性、衝動性の症状を改善させます。しかし、個人差が大きいため投薬量は慎重に調節される必要があります。
行動療法
行動療法は、認知行動療法に基づく心理社会的アプローチです。主に以下のような対応が含まれます。
- ペアレント・トレーニング
- 行動修正法
- 社会性スキルトレーニング
親や本人への指導を通じて、より適切な行動パターンを身につけていくことが目的です。また、学校や職場との連携も重視されます。
まとめ
ADHDは、不注意、多動性、衝動性という3つの主症状から、様々な二次障害や行動上の問題、対人関係の問題を引き起こしやすい発達障害です。その原因は脳の発達の偏りや神経伝達物質の異常、遺伝や環境要因が関係していると考えられています。早期からの適切な診断と治療が大切で、薬物療法と心理社会的アプローチを組み合わせた包括的な支援が重要となります。ADHDの方々が日常生活や社会生活を送れるよう、医療、福祉、教育の各分野から理解とサポートを継続していくことが求められます。
よくある質問
ADHDの主な症状は何ですか?
ADHDの主な症状は、不注意、多動性、衝動性の3つです。不注意では、集中力の欠如や忘れ物が多いのが特徴です。多動性では、落ち着きがなく常に動き回っていることが見られます。衝動性では、思考を制御するのが難しく、危険な行動をしてしまうことがあります。
ADHDの原因は何ですか?
ADHDの正確な原因は解明されていませんが、脳の発達の偏りによる前頭前野の機能低下や、神経伝達物質の異常が関与していると考えられています。また、遺伝的な要因や環境要因、出生時の問題なども関係していると指摘されています。
ADHDの診断はどのように行われますか?
ADHDの診断は医師による詳しい問診や行動チェックリストを用いた評価、発達歴の確認、他の障害との除外診断などを通して総合的に行われます。症状の有無や程度、多様な場面での現れ方などを総合的に判断して診断されます。
ADHDの治療はどのように行われますか?
ADHDの治療は薬物療法と心理社会的アプローチを組み合わせて行われることが多です。薬物療法では神経伝達物質の調整に効果的な薬が使用され、行動療法では適切な行動パターンの獲得を目指します。両者を組み合わせることで、ADHDの症状改善に向けた包括的な支援が行われます。


