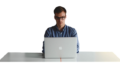はじめに
学習障害は、知的な発達に遅れはないにもかかわらず、読み書き、計算、推論などの特定の領域で著しい困難を示す神経発達症群の一つです。子どもたちの健やかな成長にとって、学習障害への適切な対応は非常に重要な課題となっています。本記事では、学習障害の実態と症状、支援の在り方について、さまざまな角度から掘り下げていきます。
学習障害の概要

まず、学習障害の全体像を把握しましょう。学習障害には主に読字障害、書字障害、算数障害の3つのタイプがあり、1つのタイプに限らず複数の障害が重複する場合もあります。これらの障害は生まれつき備わっているものであり、年齢を重ねるにつれてその特徴が顕在化していきます。
読字障害(ディスレクシア)
読字障害は、文字の認識や音韻認識の困難さから、読む能力に遅れが生じる障害です。文字と音の対応関係をうまく結びつけられず、読み間違いが多くなったり、文章の意味を理解するのが難しくなる傾向にあります。
読字障害のある子どもは、次のような特徴が見られます。
- 単語の一部分しか読めない
- 文字や単語を入れ替えて読んでしまう
- 指で追いながら読まないと難しい
- 同じ単語を何度も繰り返し読んでしまう
書字障害(ディスグラフィア)
書字障害は、脳内での情報伝達の問題から、文字を書くことに著しい困難を示す障害です。書く動作自体は問題なく行えるものの、正しい文字を思い浮かべて書き表すことが極端に難しくなります。
書字障害のある子どもは、以下のような特徴があります。
- 文字のつくりがぎこちない
- 文字の一部分が欠けている
- 文字の向きが一定でない
- 行間やマス目からはみ出して書いてしまう
算数障害(ディスカリキュリア)
算数障害は、数の概念理解や計算、推論に困難があり、算数や数学の学習に大きな影響を与える障害です。具体的な数の操作は可能でも、数値の抽象的な捉え方やさまざまな計算処理に障害が生じます。
算数障害のある子どもは、次のような様子が見られます。
- 足し算と引き算がうまくいかない
- 計算の順序が分からない
- 時計の読み方や概念が理解できない
- 方向感覚や位置関係の把握が苦手
診断と支援
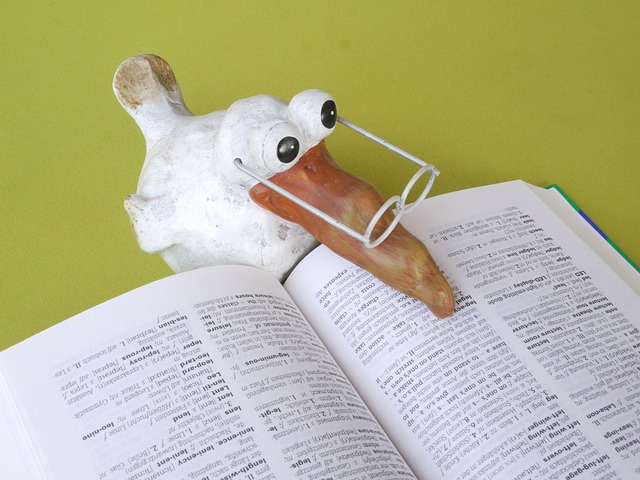
学習障害は、知的障害や視聴覚の問題とは異なる特性を持つため、適切な検査と診断が欠かせません。また、その上で個別の特性に合わせた支援を行うことが何より大切です。
診断の過程
学習障害の診断には、知能検査や認知機能検査、学力検査などが行われます。これらの検査結果から、子どもの実際の能力と学習面での困難さのギャップを確認し、学習障害の有無を見極めていきます。
診断の際は、医師や臨床心理士、言語聴覚士など、さまざまな専門家が関わります。子どもの実態を多角的に評価し、後述する二次障害の有無も確認して、総合的に判断を下していきます。
二次障害への対応
学習障害には、そのまま放置すると二次障害が起こるリスクがあります。学習の遅れから、やる気を失ったり自尊心が低下したりすることで、不登校やひきこもり、うつ病などを併発することもあるのです。
こうした二次障害を防ぐには、早期発見と適切な支援が何より重要です。子どもの強みを活かしながら、苦手な領域をサポートしていく姿勢が求められます。また、専門家や家族、学校現場との緊密な連携を図り、子ども一人ひとりに合った包括的な支援を行っていく必要があります。
支援の実践例
学習障害のある子どもへの支援は、多岐にわたります。以下に具体例を挙げます。
| 支援内容 | 具体例 |
|---|---|
| 視覚的補助具の活用 | 拡大文字の使用、図解や絵の活用 |
| ICT機器の導入 | 音声読み上げソフト、ワープロ、タブレット端末の使用 |
| 学習環境の調整 | 別室受験、時間延長、指導補助員の配置 |
| 指導方法の工夫 | 復唱練習、ルビの活用、個別最適化された指導 |
このように、さまざまな支援が考えられますが、一番大切なのは子ども一人ひとりの特性に合わせて柔軟に対応することです。試行錯誤を重ねながら、その子なりの学び方を見つけていくプロセスが欠かせません。
社会の理解促進

学習障害の子どもたちを適切に支援していくためには、社会全体での理解が不可欠です。偏った見方や誤解から生じる心理的な負担を軽減し、それぞれの強みを活かせる環境づくりに取り組む必要があります。
ステレオタイプへの対処
学習障害に対しては、「怠けている」「努力が足りない」といったステレオタイプの見方がよくあります。しかし、学習障害は脳の機能の問題に起因するものであり、本人の意志とは関係がありません。
こうした偏った見方を払拭し、学習障害の本質を正しく理解することが重要です。学校や職場、地域社会全体で、正しい知識を共有していく必要があるでしょう。
多様性の尊重
学習障害は、人間の多様性を表す一つの在り方です。障害のある人もない人も、互いに異なる特性を持つ存在として尊重し合うことが大切になります。
差別的な言動を排し、多様性を包摂する社会を築いていく必要があります。一人ひとりが心を開き、互いの個性を認め合うことで、より豊かな社会が実現できるはずです。
当事者の視点の重視
学習障害の理解を深めるためには、当事者の体験に耳を傾けることが欠かせません。本人たちはどのような困難を抱え、どのような支援を求めているのか、その声に学ぶことが重要です。
当事者が主体的に働きかけられる機会を設け、支援のあり方を一緒に考えていくプロセスが必要不可欠です。そうした対話を通じて、本当に求められる支援を提供できるはずです。
まとめ
学習障害は、外見上はわかりにくい障害ですが、適切な理解と支援があれば、十分に力を発揮できる可能性を秘めています。一人ひとりの特性に合わせた柔軟な指導を行い、強みを伸ばしながら苦手な部分をサポートしていくことが大切です。
同時に、社会全体で学習障害への理解を深め、多様性を尊重し合う環境づくりに取り組む必要があります。当事者の声に耳を傾け、本人らしく生きられる社会を目指していきましょう。
よくある質問
学習障害とはどのような障害ですか?
学習障害は、知的な発達に遅れはないにもかかわらず、読み書き、計算、推論などの特定の領域で著しい困難を示す神経発達症群の一つです。読字障害、書字障害、算数障害の3つのタイプがあり、複数の障害が重複することもあります。生まれつき備わっているものであり、年齢とともに特徴が顕在化していきます。
学習障害にはどのような特徴がありますか?
読字障害のある子どもは、単語の一部分しか読めなかったり、文字や単語を入れ替えて読んでしまったりする傾向があります。書字障害のある子どもは、文字のつくりがぎこちなかったり、文字の一部分が欠けていたりします。算数障害のある子どもは、足し算と引き算がうまくいかなかったり、計算の順序が分からなかったりします。
学習障害の子どもにはどのような支援が行われますか?
学習障害のある子どもへの支援には、拡大文字の使用や図解、ICT機器の導入などの視覚的補助具の活用、別室受験や時間延長などの学習環境の調整、復唱練習やルビの活用などの指導方法の工夫などが行われます。一人一人の特性に合わせて柔軟に対応し、本人なりの学び方を見つけていくプロセスが大切です。
学習障害への理解を深めるためには何が重要ですか?
学習障害への理解を深めるためには、ステレオタイプの見方を払拭し、本質を正しく理解することが重要です。障害のある人もない人も、互いの個性を尊重し合う多様性を包摂する社会を築く必要があります。当事者の体験に耳を傾け、本人らしく生きられる支援のあり方を一緒に考えていくことが欠かせません。