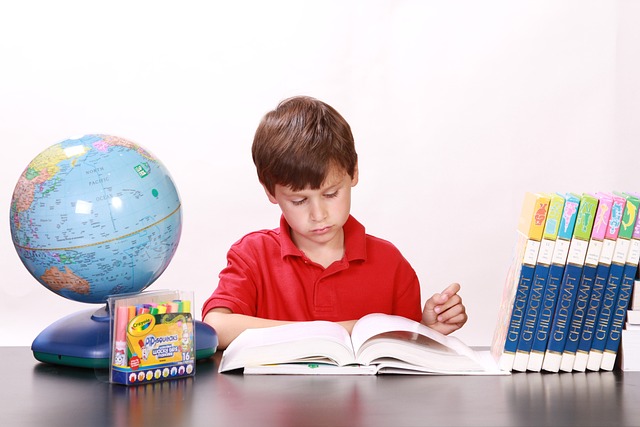はじめに
発達障害のある子どもや生徒の進路選択は、多くの保護者や本人にとって大きな不安と課題となっています。発達障害には様々な特性があり、一人ひとりに合わせた適切な支援が必要不可欠です。本ブログでは、発達障害のある子どもや生徒の進路選択について、さまざまな観点から詳しく解説していきます。
発達障害の理解

発達障害を理解するためには、まずその種類と特徴を知ることが重要です。発達障害には自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などがあり、それぞれ異なる特性を持っています。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症(ASD)は、社会的コミュニケーションおよび相互関係の障害、限定された興味や反復的な行動パターンを特徴とする発達障害です。ASDの人は、言語の使用の質的な障害や対人交流の困難さ、反復性のある行動や興味関心の偏りなどがみられます。
ASDの特性から、学校生活においては対人関係の構築や社会的状況の理解が難しく、集中力の持続も課題となります。進路選択の際は、本人の特性に合わせた環境が重要になってきます。
注意欠陥・多動性障害(ADHD)
注意欠陥・多動性障害(ADHD)は、年齢や発達に比べて著しい注意力の欠如、多動、impulsivity(衝動性)を主な特徴とする発達障害です。ADHDの人は、集中力が持続しにくく、落ち着きがない行動がみられます。
学校生活では授業に集中することが難しく、制限のある環境では落ち着きのない行動が目立ちます。進路選択では、ADHDの特性に配慮した環境や、得意分野を生かせる職種を探すことが重要です。
学習障害(LD)
学習障害(LD)は、平均的な知的発達があるにもかかわらず、聞く、話す、読む、書く、推論する、または数学的推理に関する特定の能力の障害があり、それらの障害が顕著で、指導に適切な教育的措置を講じても克服できない状態をいいます。
LDの人は、読む、書く、計算するなどの特定の分野で困難を抱えています。進路を選ぶ際は、得意な分野を活かせるような職種や環境を見つけることが大切です。
発達障害のある子どもの進路選択
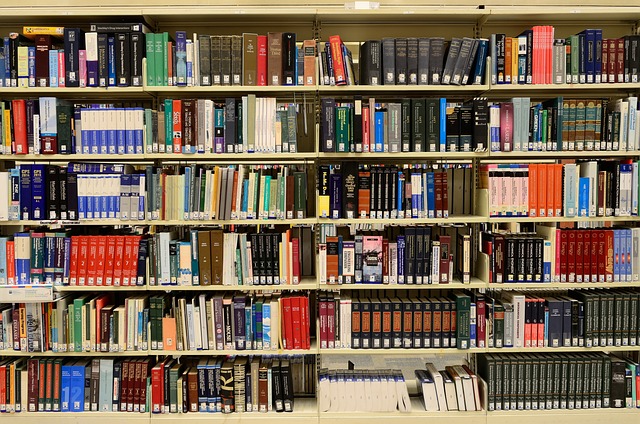
発達障害のある子どもの進路選択は、一人ひとりの特性に合わせて慎重に検討する必要があります。小学校から高校、そして就職や進学など、それぞれの段階で選択肢は変わってきます。
小学校
小学校では、通常学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校などの選択肢があります。子どもの発達障害の程度や特性に合わせて、適切な学習環境を選びます。
通常学級では発達障害の理解があまりなく、支援が不足する可能性がありますが、通級指導教室や特別支援学級を利用すれば、専門的な指導を受けられます。特別支援学校は発達障害児教育に特化しており、手厚い支援が受けられます。
中学校
中学校進学時には、以下のような選択肢があります。
- 普通中学校の通常学級
- 普通中学校の特別支援学級
- 特別支援学校の中学部
- 中高一貫教育校
中学校では、基礎学力の定着や進路選択の指導が重要となります。発達障害の状況に合わせて、適切な環境を選びます。中高一貫教育校では、高校進学が確実となりますが、受験競争が課題となります。
高校
高校進学には、以下のような選択肢があります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 普通科高校 | 全日制、定時制、通信制などの種類がある。発達障害への支援体制が不十分な場合がある。 |
| 専門学科高校 | 職業教育に特化しており、実習や資格取得に適している。しかし学業が難しい場合もある。 |
| 特別支援学校高等部 | 発達障害教育に特化しており、手厚い支援を受けられる。生徒数が少ないため、選択肢が限られる。 |
高校選びでは、本人の特性や進路希望に合わせて、適切な学習環境を見つけることが重要です。発達障害者支援の専門家や、在籍校の教員に相談するのがおすすめです。
発達障害のある生徒の進路選択

発達障害のある生徒の進路選択は、高校卒業後に大きく分かれます。進学、就職、そして「働く準備」の3つの選択肢があり、一人ひとりの特性や希望に合わせて検討する必要があります。
進学
発達障害のある生徒が進学を選ぶ場合、以下のような選択肢があります。
- 大学(国公立、私立)
- 短期大学
- 専門学校
- 各種学校
大学や専門学校では、発達障害の理解があり、合理的配慮が受けられる機関を選ぶことが重要です。試験時間の延長や課題提出期限の延長、ノートテイク支援などの配慮があります。
また、障害者支援制度を利用することで、学費の一部が補助される場合もあります。大学入試センター試験や個別学力検査において、発達障害のある受験生への特別な措置もあります。
就職
発達障害のある生徒が就職を希望する場合、以下のような選択肢があります。
- 一般企業就職
- 障害者雇用促進制度を活用した就職
- 福祉的就労
- 自営業・フリーランス
発達障害がある方の特性を理解し、適切な配慮をしてくれる企業や職場を選ぶことが大切です。障害者雇用促進制度や就労移行支援事業などを活用すると、様々な支援が受けられます。
また、地域の障害者就業・生活支援センターに相談すれば、本人の特性に合った職種や求人情報を提供してくれます。職場実習や職場開拓支援なども活用できます。
働く準備
発達障害のある生徒の中には、すぐに就職するのが難しい場合もあります。そのような場合は、「働く準備」として以下のようなサービスを利用することができます。
- 生活訓練(家事、金銭管理、時間管理など)
- 就労移行支援事業所での職業訓練
- 障害者職業能力開発校
- サポート校(専門学校への入学準備)
就労移行支援事業所では、本人の特性に合わせた職業訓練や就職活動支援を受けられます。障害者職業能力開発校では、実践的な職業訓練を受けることができます。
このように発達障害のある人の就労に向けた様々な支援制度があり、本人のペースに合わせて活用することが重要です。
まとめ
発達障害のある子どもや生徒の進路選択は、一人ひとりの特性に合わせて慎重に検討する必要があります。小学校から高校、そして進学や就職と、ライフステージに合わせて選択肢が変わってきます。
発達障害への理解が深まり、様々な支援制度が整備されてきましたが、本人や保護者が正しい情報を得ることが何より大切です。学校の先生や専門家に相談しながら、本人の特性を活かせる進路を見つけていくことが重要です。
発達障害のある子どもや生徒一人ひとりが、自分に合った進路を歩めるよう、周囲の理解と適切な支援を受けられる環境づくりが求められています。
よくある質問
発達障害のある子どもの進路選択の選択肢は何ですか?
発達障害のある子どもの進路選択には、小学校から高校、そして就職や進学など、ライフステージに応じて様々な選択肢があります。小学校では通常学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校などが、中学校では普通中学校の通常学級や特別支援学級、特別支援学校の中学部などが、高校では普通科高校、専門学科高校、特別支援学校高等部などが選択肢となります。一人ひとりの特性に合わせて、適切な学習環境を選択することが重要です。
発達障害のある生徒の高校卒業後の進路選択肢は何ですか?
発達障害のある生徒の高校卒業後の進路選択肢は、大きく分けて進学、就職、そして「働く準備」の3つがあります。進学では大学、短期大学、専門学校などがあり、就職では一般企業就職、障害者雇用制度を活用した就職、福祉的就労、自営業・フリーランスなどが選択肢となります。また、すぐに就職が難しい場合は、生活訓練や就労移行支援事業所での職業訓練など「働く準備」のためのサービスも活用できます。
発達障害のある生徒が進学を選ぶ際の留意点は何ですか?
発達障害のある生徒が進学を選ぶ場合、発達障害の理解があり、合理的配慮が受けられる大学や専門学校を選ぶことが重要です。試験時間の延長や課題提出期限の延長、ノートテイク支援などの配慮が受けられます。また、障害者支援制度を利用すれば、学費の一部が補助される場合もあります。大学入試センター試験や個別学力検査においても、発達障害のある受験生への特別な措置があります。
発達障害のある生徒が就職を希望する際の支援制度は何ですか?
発達障害のある生徒が就職を希望する際は、障害者雇用促進制度や就労移行支援事業などを活用することで、様々な支援を受けられます。障害者の特性を理解し、適切な配慮をしてくれる企業や職場を見つけることが大切です。また、地域の障害者就業・生活支援センターに相談すれば、本人の特性に合った職種や求人情報を提供してくれます。職場実習や職場開拓支援なども活用できます。